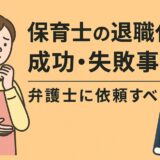「退職したのに、会社から損害賠償を請求された」
「内容証明が届いて不安で眠れない」
このような相談が近年増えています。退職後に突然、元職場から法的な請求を受けると、多くの人が「自分が悪いのか」「支払わなければ裁判になるのか」と動揺してしまいます。
しかし、会社から損害賠償を請求されたとしても、必ずしも支払い義務が生じるわけではありません。多くの場合、請求内容に法的な根拠がなく、冷静に対処すればトラブルを防ぐことが可能です。焦って和解や支払いに応じる前に、まずは請求の正当性を確認し、適切な対応を取ることが重要です。
本記事では、退職後に損害賠償請求されたときの主な原因、実際に起こり得る事例、そして正しい対処法を弁護士監修の視点から詳しく解説します。
弊所弁護士法人みやびでは、損害賠償請求の対応はもちろんのこと、在職中に賠償請求される気配がある場合、退職代行という形で、賠償請求されない安全な退職を実現することができます。まずはお気軽にご相談ください。
退職後に会社から損害賠償請求された!まず確認すべき3つのポイント
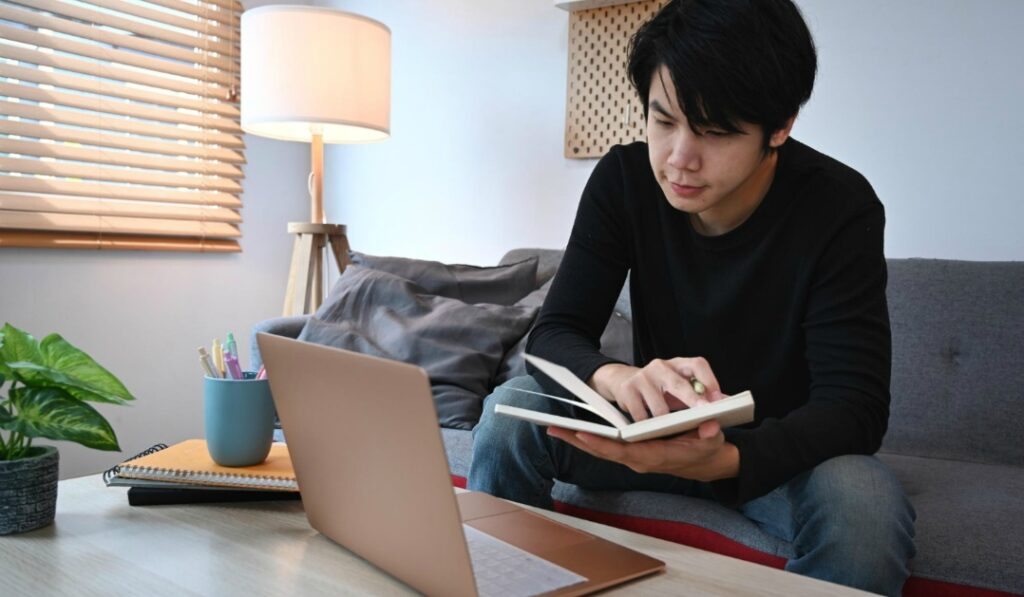
退職後に会社から突然「損害賠償請求書」や「内容証明郵便」が届くと、驚きと不安で冷静さを失いがちです。しかし、ここで焦って行動すると、不要な支払いやトラブルの長期化につながる恐れがあります。
請求書や内容証明に記載された「理由」と「金額」を確認する
最初に確認すべきは、会社が何を理由に、いくらの損害賠償を請求しているのかという点です。多くの場合、「業務引継ぎを怠った」「顧客情報を持ち出した」「会社に損害を与えた」などの曖昧な表現が記載されています。もし具体的な損害額や証拠が提示されていない場合、その請求は法的根拠に乏しい可能性があります。焦って支払わず、まずは内容を精査してください。
請求に法的な根拠があるかを判断する
会社が損害賠償を請求するには、労働契約や民法に基づいた法的根拠が必要です。たとえば、従業員が故意または重大な過失で会社に損害を与えた場合のみ、損害賠償が認められます。単なる退職や引継ぎ不足だけでは、原則として請求は成立しません。請求書の内容を鵜呑みにせず、どの法律に基づく主張なのかを必ず確認しましょう。
弁護士または専門機関に相談する
退職後の損害賠償請求は、個人で対応するにはリスクが高い問題です。内容証明や請求書に対して誤った返答をすると、相手方に「請求を認めた」と誤解されることもあります。弁護士や法律事務所に相談すれば、請求内容の法的妥当性を確認し、不当な請求であれば正式に反論することが可能です。初期対応を誤らないことが、トラブルを最小限に抑える最大のポイントです。
なぜ退職後に損害賠償を請求されるのか?主な理由と対策

退職後に会社から損害賠償を請求される背景には、いくつかの共通したパターンがあります。多くのケースでは、従業員が故意に損害を与えたわけではなく、会社側の一方的な判断や誤解による請求も少なくありません。ここでは、よくある理由と、その対策を具体的に見ていきましょう。
機密情報漏洩や競業避止義務違反のケース
退職後に競合企業へ転職したり、独立して同業ビジネスを始めた場合、会社が「営業秘密を持ち出した」「顧客情報を使用した」と主張することがあります。特に、在職中に秘密保持契約(NDA)や競業避止条項を結んでいた場合、これを根拠に損害賠償を請求されることがあります。
対策としては、退職前に社内データや顧客リストなどの個人持ち出しを一切行わないことが重要です。また、退職後に同業へ転職する場合は、契約書の内容を確認し、競業禁止期間の有無を把握しておきましょう。実際には、競業避止義務が無制限に認められることはなく、合理的な範囲を超える場合は無効と判断されるケースもあります。
研修費用や留学費用の返還を求められるケース
「入社時にかかった研修費用」や「海外研修・留学費の会社負担分」を退職後に返還請求されるトラブルも見られます。企業が一定期間の勤務を前提に費用を負担していた場合、「短期退職による契約違反」とみなされることがあります。
ただし、民法上、労働契約における「損害賠償予定」や「違約金の定め」は原則禁止されています。そのため、契約書に返還義務の記載があっても、実際に裁判で全額が認められるケースはごく稀です。法的に有効な返還請求かどうかを確認するためにも、弁護士に契約内容をチェックしてもらうと安心です。
退職時の引継ぎ不足や突然の退職による混乱
「引継ぎが不十分だった」「突然辞めたせいで業務に支障が出た」として損害賠償を請求されることもあります。しかし、退職は労働者の自由であり、民法627条に基づき、原則として2週間の予告期間を設ければ法的に問題はありません。
実際には、会社が「損害を被った」と主張しても、具体的な損害額や因果関係を立証できない限り、請求は成立しません。トラブルを避けるには、退職の意思を正式な書面で伝え、引継ぎの有無を記録に残しておくことが有効です。
退職後に損害賠償を請求される場合、多くは会社側が従業員の「退職の仕方」に不満を持っているケースです。法的な根拠に基づかない請求がほとんどのため、感情的に謝罪や支払いを行わず、冷静に対処することが最善の防衛策です。
嫌がらせ目的で損害賠償を請求されるケース
退職後、明確な損害がないにもかかわらず「会社に迷惑をかけた」「引継ぎが不十分だった」といった曖昧な理由で損害賠償を請求されるケースもあります。こうした請求は、実際には法的根拠がなく、従業員を心理的に追い詰めることを目的とした“嫌がらせ的請求”であることが多いです。
特に、パワハラ体質のある上司や、ブラック企業に多く見られる傾向です。「退職の仕方が気に入らない」「他の社員への見せしめにしたい」といった感情的な理由で請求されることもあります。しかし、損害賠償はあくまで“実際の損害”が発生している場合にのみ成立するものであり、嫌がらせや報復目的での請求は法的に認められません。
もしこのような内容証明や請求書が届いた場合は、直接会社に連絡せず、弁護士を通じて正式に対応することが大切です。法的に無効な請求であることを明確に示せば、ほとんどのケースはそれ以上の接触が止まります。精神的に追い詰められる前に、専門家に介入を依頼するのが最も安全な方法です。
退職後の損害賠償請求で実際に起きた事例と企業法務の見解

退職後に会社から損害賠償請求を受けたケースは、業種や職種を問わず実際に発生しています。しかし、実際に裁判で会社側の請求が全面的に認められる事例は少なく、ほとんどの場合、企業の主張が退けられています。ここでは代表的な事例を紹介し、企業法務の観点からその法的判断を解説します。
顧客情報の持ち出しを理由に損害賠償を請求されたケース
ある営業職の従業員が退職後に競合企業へ転職したところ、前職の会社から「顧客リストを持ち出した」として300万円の損害賠償を請求されました。裁判では、従業員が私物パソコンにデータを保存していた事実は確認されましたが、実際に顧客情報を利用して営業活動を行った証拠がなかったため、請求は棄却されました。このように、単に「データを持っていた」というだけでは損害を立証できず、会社が請求を通すのは非常に困難です。
退職後の引き抜き行為で裁判に発展したケース
管理職が独立後に元部下を複数名引き抜いたとして、元の会社から損害賠償を請求されたケースがあります。会社は「組織運営に重大な損害を与えた」と主張しましたが、裁判では「退職後の引き抜き自体は違法ではなく、在職中に引き抜きを画策していた証拠もない」として、請求は一部のみ認められました。
留学・研修費用を返還請求されたケース
入社時に「3年以上勤務しなければ研修費用を返還する」という誓約書を提出していた従業員が、2年で退職したところ、会社から留学費用100万円の返還を求められました。裁判では、誓約書の存在は認められたものの、「返還義務を一律に定めるのは労働基準法第16条に違反する」と判断され、請求は無効とされました。
この判例からも分かるように、従業員に一方的な負担を強いる契約は法的に無効とされることが多く、返還請求が認められるのはごく例外的な場合のみです。企業法務の立場でも、研修費返還契約は慎重に扱うべきとされています。
ブラック企業による報復的な損害賠償請求
パワハラや長時間労働が原因で退職した従業員に対し、「会社に迷惑をかけた」「後任が見つからず損害が出た」として請求を行ったブラック企業も存在します。しかし、実際には具体的な損害額の立証ができないため、裁判所はほとんどのケースで会社側の主張を退けています。
企業法務上も、従業員の退職は正当な権利であり、引き止めや報復目的での請求は法的に無効です。弁護士を通じて正式に対応することで、会社からの嫌がらせや接触を防ぐことができます。
会社を退職後の損害賠償が裁判で認められるケースと、認められないケースの違い

退職後に会社から損害賠償を請求されても、すべての請求が法的に認められるわけではありません。実際の裁判例をみると、会社側の請求が棄却されるケースが大半です。ここでは、裁判で損害賠償が「認められる場合」と「認められない場合」の違いを明確に整理します。
裁判で損害賠償が認められるケース
損害賠償が成立するためには、会社側が「損害の発生」「労働者の故意または重大な過失」「損害との因果関係」の3つを立証する必要があります。これらが明確に証明された場合のみ、損害賠償が認められる可能性があります。
たとえば、従業員が社内機密を外部に流出させ、実際に取引先が離れたなど、具体的な損害が発生した場合です。また、故意に業務データを削除した、会社の備品を破壊したといった明確な過失行為も対象になります。ただし、損害額の算定には客観的証拠が求められ、会社側が「精神的損害」など抽象的な理由を主張しても認められません。
裁判で損害賠償が認められないケース
一方で、会社が感情的・報復的な理由で損害賠償を請求するケースでは、ほとんど認められません。たとえば、「突然辞めたせいで迷惑をかけた」「他の社員の士気が下がった」などの抽象的な主張では、損害と因果関係を立証できないため、請求は棄却されます。
また、労働者に軽微な過失があっても、業務上のリスクは企業が負担すべきとされており、「使用者責任」の原則から、企業側に請求権は発生しません。特にブラック企業では、この原則を無視して不当請求を行うケースが多く見られますが、法的には一切支払う義務はありません。
損害と因果関係の立証責任に関する基本ルール
労働契約関係では、会社が損害賠償を請求する場合、損害額や因果関係を立証する責任は会社側にあります。つまり、従業員が「損害を与えた」という主張を否定するために、労働者が証拠を出す必要は基本的にありません。
会社側が請求書や内容証明を送ってきたとしても、具体的な損害の根拠が明示されていなければ、その請求には法的効力がありません。もし請求書に「引継ぎが不十分だった」「勤務態度が悪かった」など曖昧な文言しかない場合は、弁護士に依頼して正式に「法的根拠の提示を求める」通知を出すのが最も安全です。
会社を退職後に損害賠償請求されたときの初期対応と取るべき行動

退職後、突然会社から「損害賠償請求書」や「内容証明郵便」が届くと、多くの人は驚きや不安で冷静さを失ってしまいます。しかし、ほとんどの請求は法的根拠が乏しく、冷静に対処すればトラブルを防ぐことが可能です。ここでは、損害賠償請求を受けたときの初期対応の流れと注意点を解説します。
支払いや返信をせず、請求内容を冷静に確認する
会社から損害賠償を請求された場合、まず絶対に「すぐ支払う」「感情的に返信する」「自力で示談交渉に向かう」といった行動は避けましょう。請求書や内容証明の文面を落ち着いて確認し、「請求の根拠」「損害額」「証拠の有無」をチェックします。
また、口頭や電話でのやり取りは避け、すべて書面で記録を残すようにしましょう。企業によっては「支払う意志がある」と誤解されるリスクがあります。
内容証明や請求書は破棄せず、証拠として保管する
会社から届いた書類は、すべて証拠として保管してください。内容証明郵便やメールには、送付日・内容・発信者の証拠力があり、後の法的対応において有利に働きます。請求の内容が不当であることを証明するためには、企業側の言い分を正確に記録しておくことが重要です。
また、SNSや社内チャットでのやり取りも、ハラスメントや威圧的発言の証拠として有効です。削除される前にスクリーンショットを取って保存しておきましょう。
弁護士に相談し、今後の対応を一任する
請求内容を個人で判断するのは危険です。特に損害賠償請求には法的専門知識が必要であり、弁護士が介入することで会社側の主張が法的に成立するかを冷静に判断できます。弁護士が代理人として対応すれば、会社との直接連絡を避けられ、心理的負担も軽減されます。
また、弁護士が介入した段階で、多くの企業は「不当請求が通らない」と判断し、早期に請求を取り下げる傾向にあります。請求額が高額であっても、焦らず専門家に対応を任せましょう。
在職中に退職代行:退職後に損害賠償請求を回避する方法

退職後に会社から損害賠償を請求されるケースの多くは、退職の伝え方や手続きの進め方に問題があった場合です。特に、感情的なやり取りや無断欠勤を経て退職した場合、会社が「業務に支障が出た」と主張する可能性があります。こうしたトラブルを避けるためには、在職中の段階で退職代行を利用し、法的に正しい手続きで退職を進めることが有効です。
退職代行を使えば「退職意思の到達」を正式に証明できる
民法第627条では、労働者は退職の自由を持ち、会社の承諾は不要とされています。ただし、その意思が会社に「到達」していなければ法的に有効になりません。退職代行を通じて通知を行うことで、会社に対して正式に退職の意思を届けた証拠を残せます。これにより、退職後に「無断欠勤による損害」などの請求をされるリスクを大幅に減らすことが可能です。
引継ぎや業務放棄を理由とした請求を防げる
ブラック企業では、「引継ぎをしなかったから損害が出た」「業務を放棄した」などの理由で損害賠償を請求するケースがあります。しかし、退職代行を通じて弁護士が代理通知を行えば、退職日までの法的手続きや引継ぎに関する責任の範囲を明確にできます。弁護士が介入していることで、会社側も軽率な請求や脅迫的な発言を控える傾向にあります。
感情的な対立を避けて円満退職に導ける
退職の場面では、上司や人事担当者とのやり取りが感情的になり、思わぬトラブルを生むことがあります。退職代行を利用すれば、本人が直接会社と接触する必要がなく、冷静かつ法的に適切な形で退職を進められます。これにより、退職後に「不誠実な態度だった」として不当請求をされるリスクも回避できます。
会社退職後の損害賠償請求に応じる前に確認すべき法的ルール

会社から損害賠償を請求されたとしても、法的にその請求が有効であるとは限りません。退職後に慌てて支払ってしまうと、取り戻せないケースもあります。ここでは、請求に応じる前に確認すべき基本的な法律ルールと、労働者を守るための仕組みを解説します。
労働契約では「賠償予定の禁止」が原則
労働基準法第16条では、あらかじめ損害賠償額を定めておく「賠償予定契約」を禁止しています。これは、労働者が会社に不利な契約を強要されないようにするための規定です。たとえば、就業規則や雇用契約書に「退職したら研修費を全額返還する」などの条文があっても、法的には無効となる可能性が高いです。
実際、裁判でも「一方的に高額な返還義務を課す契約は労働者保護の趣旨に反する」と判断された事例が多くあります。つまり、会社側がどれだけ「契約書に書いてある」と主張しても、それだけで支払い義務が発生するわけではありません。
会社が損害を立証できない場合は支払い不要
損害賠償が成立するためには、会社が「損害の発生」「従業員の故意・過失」「損害との因果関係」を立証する必要があります。これらの要素が欠けている場合、請求は認められません。特に「突然辞めたせいで売上が落ちた」といった抽象的な主張では、裁判で損害を証明することはほぼ不可能です。
また、会社の経営リスクや業務運営上の損失は、基本的に使用者(会社)が負担すべきものであり、従業員個人に転嫁することは許されません。この原則を理解しておけば、不当な請求に惑わされることはありません。
和解金や示談金の提案には注意が必要
一部の企業は、法的根拠がないにもかかわらず「トラブルを穏便に解決したい」として、和解金や示談金の支払いを求めてくることがあります。このような提案は、労働者の不安心理につけ込んだ手口である場合が多く、慎重な対応が必要です。
金額の多寡にかかわらず、安易に支払うと「責任を認めた」と判断されるリスクもあります。少しでも不当性を感じたら、弁護士に相談し、法的に妥当な金額かどうかを確認しましょう。
損害賠償を請求されたときに弁護士に相談すべき理由と依頼のタイミング

退職後に損害賠償を請求された場合、最も重要なのは「早めに弁護士へ相談すること」です。多くの人は「本当に裁判になるとは思わなかった」「請求が来てから慌てて対応した」と後悔します。ここでは、弁護士に依頼すべき理由と最適なタイミングを解説します。
法律的な有効性を判断できるのは弁護士だけ
損害賠償請求が法的に正しいのか、支払い義務があるのかを正確に判断できるのは弁護士だけです。インターネット上の体験談や一般的な知識だけでは、会社の請求が合法か不当かを見抜くことは難しく、誤った対応をしてしまうリスクがあります。
弁護士は内容証明や請求書を精査し、会社の主張が法律に基づいているかを確認します。不当な場合は正式な回答書を作成し、会社側に「今後の連絡は代理人を通すように」と通知できるため、心理的負担を軽減できます。
初期対応の早さが結果を左右する
会社からの損害賠償請求は、放置すると「支払意思がない」と判断され、訴訟へ移行するケースもあります。早い段階で弁護士が介入すれば、交渉での早期解決が可能です。多くの企業は「弁護士が入った」と分かった時点で強硬姿勢を崩す傾向があります。
また、弁護士が対応すれば、会社から本人への直接連絡を禁止することもでき、職場や実家への嫌がらせを未然に防げます。トラブルが拡大する前に相談することで、経済的・精神的な損失を最小限に抑えられます。
退職後の損害賠償トラブルは弁護士法人みやびへ相談を

退職後に会社から損害賠償を請求された場合、慌てて対応してしまうと、思わぬ不利益を被る可能性があります。会社の主張がすべて正しいわけではなく、多くのケースで法的根拠のない請求や嫌がらせが含まれています。まずは冷静に状況を整理し、専門家に相談することが解決への第一歩です。
弁護士法人みやびの特徴:法的トラブルを防ぐためのサポート体制
弁護士法人みやびでは、退職後の損害賠償請求トラブルに関する相談を多数受け付けています。会社からの不当請求や嫌がらせへの対応はもちろん、未払い賃金や慰謝料の請求など、依頼者の正当な権利を守るための法的措置も可能です。
また、退職代行を全国で提供しているため、現在在職中の方で「会社を辞めたいけど、退職後に損害賠償請求されそうで怖い」という方は、まずはLINEにて無料問い合わせください。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら
退職後の損害賠償請求に関するよくある質問(FAQ)
退職後に会社から突然、損害賠償を請求されるケースは珍しくありません。特にブラック企業では、法的根拠の乏しい請求や嫌がらせ目的の内容証明を送ってくることもあります。ここでは、退職後の損害賠償請求に関して多く寄せられる質問をまとめ、正しい知識と対応方法をわかりやすく解説します。
Q1. 退職後に会社から損害賠償請求書が届いた場合、すぐに支払うべきですか?
A. 焦って支払う必要はありません。多くの請求は法的根拠が不十分で、冷静に内容を確認すれば支払い義務がないケースが大半です。特に「引継ぎ不足」「迷惑をかけた」など曖昧な理由の場合は、弁護士に確認してから対応しましょう。
Q2. 退職後に損害賠償を請求されるのはどんなケースですか?
A. 代表的な例としては、機密情報の持ち出し、競業避止義務違反、研修費用の返還請求などがあります。ただし、これらの請求がすべて法的に有効とは限らず、会社が損害と因果関係を立証できなければ請求は成立しません。
Q3. ブラック企業が嫌がらせ目的で損害賠償を請求してくることはありますか?
A. はい、実際にあります。パワハラ体質の企業やブラック企業では、報復目的で退職者に対して不当請求を行うケースが見られます。しかし、損害の実態がない場合は法的に認められず、弁護士を通じて「根拠を示すよう通知」すれば多くは撤回されます。
Q4. 退職代行を使えば損害賠償を防げますか?
A. はい。退職代行を通じて正式に退職の意思を通知すれば、無断欠勤などを理由に「損害が出た」と主張されるリスクを防げます。弁護士が代理通知を行うことで、引継ぎ範囲の明確化や不当請求の抑止にもつながります。
Q5. 会社から内容証明が届いた場合、どのように対応すればよいですか?
A. すぐに返信したり、会社へ直接連絡するのは避けてください。まずは内容証明を開封せず保管し、弁護士に見せましょう。弁護士が請求の法的妥当性を確認し、必要に応じて正式な回答書を作成します。
Q6. 退職後に弁護士へ相談するタイミングはいつがよいですか?
A. 損害賠償請求書や内容証明が届いた時点で、すぐに相談するのが理想です。早期に弁護士が介入することで、会社との直接交渉を避けられ、トラブルが拡大する前に法的な解決を図ることができます。
Q7. 退職時に研修費や留学費の返還を求められた場合はどうすればいいですか?
A. 労働基準法第16条で「賠償予定の禁止」が定められており、退職を理由に一律で費用を請求する契約は原則として無効です。実際の裁判でも、こうした返還義務が認められるケースは極めてまれです。
Q8. 弁護士法人みやびではどのようなサポートが受けられますか?
A. 弁護士法人みやびでは、退職後の損害賠償請求への法的対応、内容証明の確認、会社との交渉、さらには在職中の退職代行まで一貫してサポートしています。全国対応でLINE無料相談も可能です。