「退職代行を使う人ってどんな人なんだろう?」
「自分も問い合わせてみたいけど、私は退職代行を使うべき?」
そう感じて検索する方は少なくありません。最近では、若手社員から管理職まで幅広い層が退職代行を利用しており、決して一部の人だけの手段ではなくなっています。
ブラック企業の勤務環境、パワハラ・人間関係の悩み、上司への恐怖心など、「自分ではもう伝えられない」という限界を感じた人が退職代行を選んでいます。
本記事では、退職代行を利用する人の特徴や背景、利用すべきかどうかの判断基準をわかりやすく解説します。さらに、非弁行為のリスクや弁護士による安心な退職方法についても詳しく紹介します。「自分も使っていいのか迷っている」という方は、ぜひ最後までお読みください。
退職代行サービスを利用する「人」の基本情報と主な理由を解説
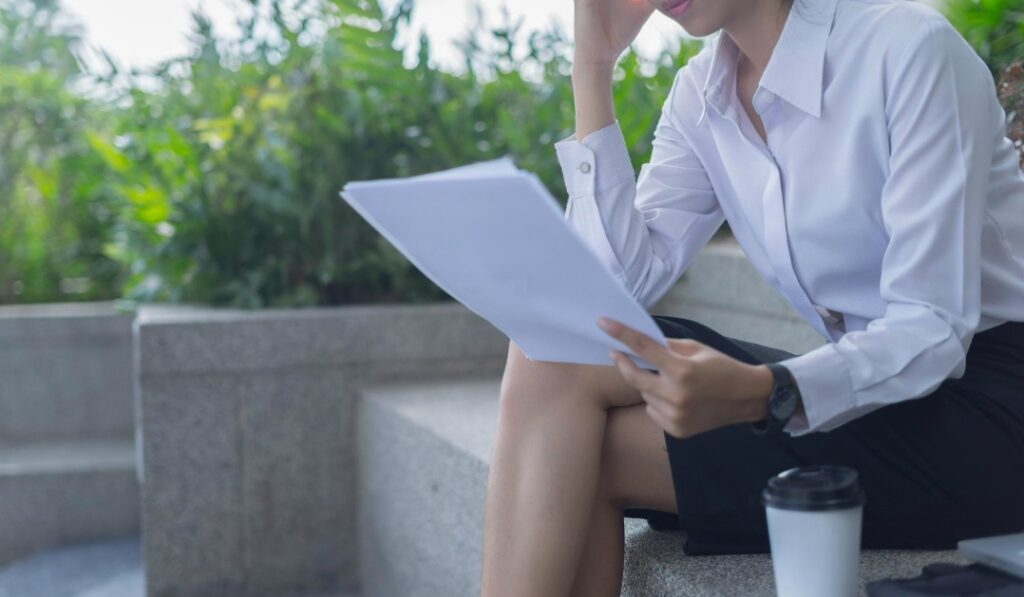
退職代行を利用する人には、一定の傾向があります。職場での人間関係や上司との関係が悪化しているケース、過重労働や精神的なストレスを抱えているケースなど、退職を「伝えること自体が困難」な状況が多く見られます。ここでは、退職代行サービスの基本的な仕組みと、実際にどんな人が利用しているのかを具体的に見ていきましょう。
退職代行とは?サービスの仕組みと役割を解説
退職代行とは、依頼者の代わりに会社へ「退職の意思」を伝えるサービスです。退職届の提出や上司への連絡を代行してくれるため、本人が職場に行かなくても円満退職が可能になります。もともとは、過酷な労働環境や人間関係に悩む従業員の「最後の手段」として生まれましたが、現在では利用者層が拡大し、一般的なサービスとして定着しつつあります。
どんな従業員・職業の人が利用しているのか
退職代行を使う人の多くは、20代〜30代の若手社員や、正社員・契約社員・アルバイトを問わず「辞めたいのに言い出せない」環境に置かれた人たちです。特に、飲食・介護・IT業界など、長時間労働や人手不足が常態化している職場では、上司の圧力や人事の拒否により退職を言い出せないケースが目立ちます。また、近年は女性や第二新卒、精神的ストレスを抱える層の利用も増加傾向にあります。
退職代行を利用する主な理由と近年の利用状況
利用理由として最も多いのは、「上司や会社に直接言うのが怖い」「何度伝えても退職を認めてもらえない」「心身が限界に達している」といった心理的負担です。2020年代以降、退職代行サービスの利用件数は年々増加しており、特にSNSの普及によって「利用は恥ずかしくない」「自分を守るための正当な手段」として受け入れられるようになりました。いまや退職代行は、個人の権利を守るための重要なサービスとして社会的認知を得ています。
退職代行の利用者に見られる特徴|人間関係・職場環境・職業の傾向

退職代行を利用する人には、明確な共通点や傾向が見られます。性別・年齢・職業を問わず、共通しているのは「職場の人間関係や労働環境に限界を感じている」という点です。ここでは、実際にどんな人が退職代行を利用しているのか、代表的な特徴を具体的に紹介します。
職場の人間関係やパワハラに悩む人が多い
退職代行の利用者で特に多いのが、上司や同僚との人間関係に悩むケースです。上司からの叱責やパワハラ、無視・圧力など、精神的に追い詰められた従業員が「直接伝える勇気が出ない」と感じて退職代行を利用します。人間関係の悪化によるストレスは、うつ病や不眠などの健康被害にもつながるため、第三者を介して安全に退職する選択が広がっています。
女性・若手社員・契約社員の利用傾向が増加
近年では、女性や20代~30代の若手社員による退職代行の利用が増えています。特に女性の場合、セクハラやマタハラといった職場トラブルに悩むケースが多く、「直接伝えるのが怖い」「感情的に否定されるのが不安」という声が多く見られます。また、契約社員やアルバイトなど非正規雇用の従業員も、雇用期間や立場の不安定さから自力での退職交渉が難しく、代行に依頼する傾向が強まっています。
ブラック企業勤務や過重労働など職場環境別の特徴
長時間労働や休日出勤が当たり前のブラック企業では、上司に退職を申し出ても「人が足りない」「辞めたら裏切り者」と言われるなど、強い引き止めが行われることがあります。こうした職場では、従業員が精神的・肉体的に限界を迎え、退職代行を使わざるを得ない状況になるケースが多いです。特に飲食・建設・介護・販売業界などでは、過重労働や人手不足の影響から退職代行の利用率が高い傾向にあります。
ブラック企業や精神的負担など、退職代行を使う理由と背景

退職代行を使う理由の多くは、単に「辞めたい」だけではなく、会社や上司との関係性、職場の体制、心身の限界など複合的な要因が絡んでいます。特にブラック企業に勤めている人や、精神的に追い詰められた状況の人ほど、退職の意思を伝えること自体が難しく、第三者の力を借りる必要があります。ここでは、退職代行を使う人の背景にある具体的な理由を見ていきましょう。
上司や人事に退職の意思を伝えにくい心理的背景
退職代行を利用する人の多くは、上司や人事に退職の意思を伝えることに強い抵抗を感じています。特に、過去に退職を申し出た際に怒鳴られたり、否定されたりした経験がある人ほど「また怒られるのでは」と恐怖心を抱きます。こうした心理的ストレスは、単なる甘えではなく、職場内での上下関係や文化が原因で生まれるものです。そのため、第三者である退職代行が介入することで、トラブルを避けつつ円滑に退職できるケースが増えています。
精神的なストレスや体調不良による限界状態
過重労働やパワハラ・モラハラなどによって、精神的・肉体的に限界を迎える従業員も少なくありません。うつ症状、不眠、食欲不振などを抱えながら働き続けるうちに、「もう出社することも難しい」という状態になる人もいます。このような場合、自分で上司に連絡することすら困難であり、退職代行が「最後の安全な手段」として選ばれています。退職を決意するタイミングは、人それぞれの限界点であることを理解する必要があります。
会社が退職を拒否・引き止めを行うケースも
一部の企業では、従業員の退職を不当に引き止めたり、「辞めるなら損害賠償を請求する」と脅したりする違法行為が行われることがあります。こうした行為は労働基準法に反し、労働者の「退職の自由」を侵害するものです。しかし、実際に現場で法的知識を持っている人は少なく、泣き寝入りしてしまうケースも多いのが現状です。退職代行を利用すれば、こうした不当な対応を避けながら、安全に退職の意思を伝えることが可能です。
退職代行を使うべき人の判断基準|本人の意思・職場対応で利用を見極める方法

「退職代行を使ってもいいのだろうか」「自分は使うべき立場なのか」と悩む人は少なくありません。退職代行はあくまで“最後の手段”ではありますが、本人の意思が尊重されない職場や、会社が退職を拒否する環境では、むしろ安全に退職するために必要な選択肢です。ここでは、退職代行の利用を検討すべき状況や判断基準を具体的に紹介します。
退職の意思を伝えても拒否される・脅される場合
「辞めたい」と伝えても、「人がいないからダメ」「次の人が決まるまで待て」などと退職を拒否される場合、退職代行の利用を検討すべきです。民法627条では、期間の定めのない雇用契約は「退職の申し出から2週間で終了」と定められています。つまり、会社の承諾がなくても退職は成立します。にもかかわらず、上司が脅迫まがいの言葉で引き止める場合は、法的トラブルを避けるためにも専門家の力を借りることが賢明です。
人事や上司が話を聞いてくれない職場環境
退職の相談をしても「忙しいから後にして」と流されたり、上司や人事がまともに話を聞いてくれない場合、職場内での解決は難しいといえます。特に、ブラック企業や縦社会の強い職場では、退職の話題を出すこと自体がタブー視されることもあります。そのような状況では、本人の意思を安全に伝える手段として退職代行を利用することで、精神的負担を大きく軽減できます。
心身の不調やうつ症状が出ているときの判断基準
仕事のストレスにより、眠れない・食欲がない・会社に行くのが怖いといった状態に陥っている場合は、できるだけ早く退職代行を検討すべきです。心身が限界に達してから無理に上司と交渉を続けると、症状が悪化し回復まで時間がかかることもあります。本人の健康と安全を最優先に考えるなら、第三者を通じて退職を進める方が現実的で、結果的に早期の社会復帰につながるケースも多くあります。
民間の退職代行業者に依頼するリスクと弁護士が対応する意義

昨今、退職代行サービスが急増する一方で、弁護士資格を持たない民間業者による「非弁行為(弁護士法違反)」が社会問題化しています。料金の安さを強調する業者の中には、退職交渉や賃金請求など、本来弁護士にしかできない法律事務を行っている例もあります。ここでは、民間業者に依頼するリスクと、弁護士が対応する退職代行の違いをわかりやすく解説します。
民間業者の非弁行為とは?知らずに違法行為に巻き込まれる危険
弁護士法第72条では、弁護士以外の者が報酬を得て法律事務を行うことを禁じています。民間の退職代行業者が退職日の交渉や有給休暇の請求、未払い賃金の交渉を行えば、非弁行為に該当するおそれがあります。依頼者が知らずに違法行為に関与してしまうケースもあり、最悪の場合「退職が無効」「業務が途中で中断」といったトラブルに発展することもあります。実際、2025年には違法業者への家宅捜索も行われており、社会的にも厳しい目が向けられています。
弁護士による退職代行はすべての交渉・請求に法的根拠がある
弁護士が行う退職代行は、退職通知の送付から、退職日や未払い残業代の請求、損害賠償の対応まで、すべて法律に基づいて行われます。弁護士には「依頼者の代理人として交渉する権限」があり、企業が強硬な態度をとった場合でも、法的手段を講じて対応可能です。また、守秘義務があるため、依頼者のプライバシーが厳重に守られます。弁護士対応の退職代行は、費用以上に安心と信頼を得られる点が大きな魅力です。
弁護士に依頼することで得られる安心と結果の違い
弁護士が対応する退職代行では、法律の知識に基づいて迅速かつ適正に手続きを進めるため、会社との無用なトラブルを防ぐことができます。特にブラック企業のように引き止めや嫌がらせが多い職場では、弁護士の介入によって態度が一変することも少なくありません。また、法的リスクを回避しつつ、有給消化や未払い賃金の回収も可能になるため、経済的にも有利です。安心して退職を完了させたい人にとって、弁護士対応の退職代行は最も確実な選択といえます。
まとめ:退職代行の利用を検討中なら弁護士法人みやびに相談を

退職代行は、職場の人間関係や精神的な負担、企業側の不当な引き止めなど、さまざまな背景をもつ人が利用しています。近年は違法な民間業者による非弁行為も増加しており、安心して退職するには「誰に依頼するか」が最も重要なポイントです。
弁護士法人みやびの退職代行は、すべての案件を弁護士が直接対応します。退職通知の送付から有給休暇の消化、未払い残業代の請求、会社との交渉まで、法的に適正な手続きで進めるため、非弁行為のリスクが一切ありません。会社からの連絡や嫌がらせもすべて弁護士が対応するため、依頼者は安心して次の生活に進むことができます。
「自分ではもう退職を伝えられない」「精神的にも限界」という方は、無理をせず弁護士に相談してください。弁護士法人みやびでは、LINE・Email・電話を通じて、問い合わせから正式依頼、退職完了まで一気通貫で弁護士が対応致します。まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら
退職代行を使う人はどんな人?に関するよくある質問(FAQ)
退職代行を利用しようか悩んでいる方の中には、「どんな人が使うの?」「本当に違法ではないの?」と不安を感じている方も多いでしょう。ここでは、退職代行の利用者像や利用時の注意点、弁護士に依頼するメリットについてよくある質問をまとめました。
Q1. 退職代行を使う人はどんな人が多いですか?
退職代行を利用するのは、上司や人事に退職を言い出せない人や、精神的・肉体的に限界を感じている人が中心です。特に20〜30代の若手社員や女性、ブラック企業に勤めている人の利用が増えています。
Q2. 退職代行を使うのは「甘え」ではありませんか?
いいえ、退職代行は甘えではありません。職場環境や人間関係によっては、自分で退職を伝えることが難しいケースもあります。安全かつ法的に正しく退職するための手段として、弁護士や労働組合による退職代行は適法な方法です。
Q3. 民間業者に依頼するとどうなりますか?
弁護士資格を持たない業者が退職交渉や未払い賃金の請求を行うと、弁護士法違反(非弁行為)に該当します。その場合、退職が無効になる・途中で業務が中断する・返金されないといったトラブルが起こるリスクがあります。
Q4. 弁護士に退職代行を依頼するとどんな対応をしてくれますか?
弁護士は退職通知の送付、退職日や有給消化の交渉、未払い残業代や損害賠償の請求など、法律に基づく対応を一括で行います。企業が違法な引き止めをした場合でも、法的手段を用いて解決できます。
Q5. どんな職場の人が退職代行を利用していますか?
長時間労働やパワハラが横行する職場、上司が感情的で話し合いができない環境、あるいは精神的に疲弊してしまった人が多い傾向です。近年は管理職や専門職の利用も増えており、職種を問わず利用されています。
Q6. 退職代行を使っても会社が退職を拒否することはありますか?
退職の自由は民法で保障されています。退職代行を通じて意思を伝えた時点で、原則として2週間後には退職が成立します。会社が拒否しても法的効力はなく、弁護士が対応すればスムーズに解決可能です。
Q7. 弁護士法人みやびに相談するメリットは何ですか?
弁護士法人みやびでは、すべての案件を弁護士が直接担当します。退職通知の送付から交渉・請求まで、非弁行為のリスクを完全に排除し、法的に安全な退職を実現します。相談は無料で、LINEや電話で即日対応可能です。








