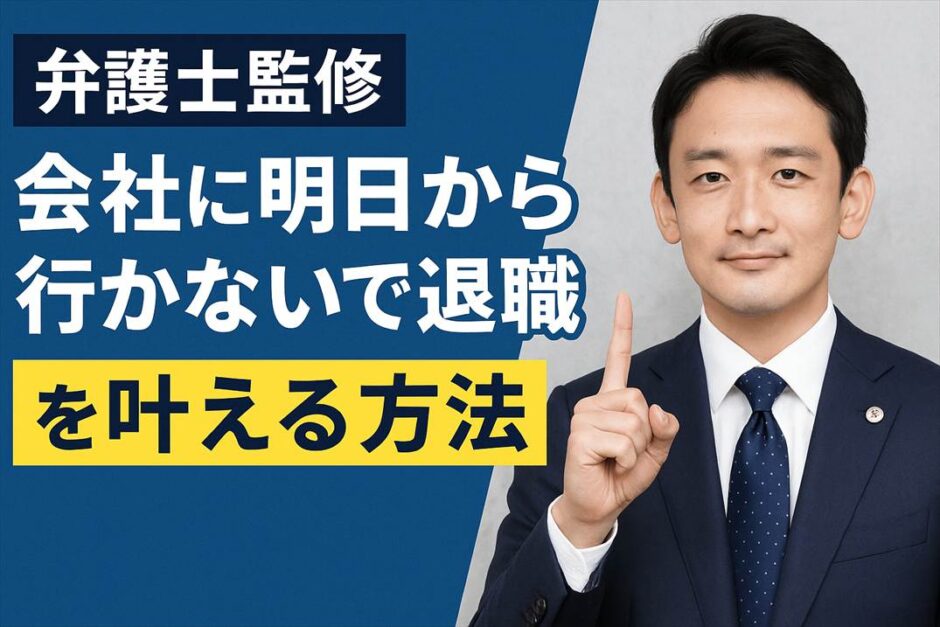「もう明日から会社に行きたくない」「限界だけど、退職を切り出す勇気が出ない」。そんな悩みを抱えている方は少なくありません。法律上「退職の自由」はすべての労働者に認められており、正しい手続きを踏めば“明日から行かない”という退職も可能です。
しかし、ネットで調べただけの法律を掲げて自力で会社上司と対峙したり、会社との交渉・方法を誤ると無断欠勤扱いになったり、損害賠償請求のリスクが発生する恐れもあります。この記事では、退職代行を全国で提供している「弁護士法人みやび」の弁護士監修のもと、即日退職を法的に成立させるための正しいルールと手続きを解説します。
弁護士法人みやびは退職代行の黎明期よりサービスを提供している老舗の法律事務所です。無料相談も可能なので、まずはLINEからお気軽にお問い合わせください。
【法律】「会社に明日から行かない」は本当に可能?退職の基本ルールと即日退職の現実

「もう行かない」と決意したとき、まず知っておくべきなのが“退職の法的ルール”です。退職は労働者の権利として保障されていますが、即日で会社を離れるには一定の条件と手続きが必要です。ここでは、法律が認める退職の自由と、即日退職が成立するケース・注意点を詳しく解説します。
法律が認める労働者の「退職の自由」(民法627条)
民法627条では、労働者は「期間の定めのない雇用」であれば、退職の意思を会社に伝えてから2週間が経過すれば自由に辞められると定められています。つまり、会社の承諾は不要で、労働者の意思だけで退職を成立させることが可能です。重要なのは、退職を伝えた日から起算して2週間で労働契約が終了するという点であり、これを知らずに「会社が許してくれないから辞められない」と思い込んでしまう人が多いのです。
即日退職が法的に認められるケースと注意点
原則として2週間の予告期間が必要ですが、特別な事情がある場合には“即日退職”も認められます。例えば、パワハラや長時間労働によって健康を害している場合、賃金の未払いが続く場合、あるいは違法な就労環境で働かされている場合などです。このように会社側が違法行為を犯している場合は、即日に労働契約の解除が可能です。ただし、証拠が乏しいまま一方的に退職を宣言するとトラブルになるため、自己判断せず、弁護士など専門家に相談してから行動するのが安全です。
「無断欠勤」と「即日退職」の違いを知ることが第一歩
会社に連絡を入れずに欠勤を続けると、法律上の「退職」ではなく「無断欠勤」とみなされます。この場合、懲戒処分や給与未払いなどの不利益を受ける可能性があります。一方で、弁護士の提供する退職代行を通じて正式に退職通知を送れば、翌日から出社しなくても“即日退職”として法的に有効です。つまり、「何も言わずに行かない」ことと「法的手続きを踏んで行かない」ことは、まったく異なる結果を生みます。正しいルールを理解し、リスクのない形で退職を進めることが重要です。
明日から出社しないで退職するには?現実的な方法と準備の流れ

「もう限界。明日から出社したくない」と思ったときに重要なのは、感情だけで行動せず、法的に正しいステップを踏むことです。退職の手続きは、たとえ翌日から出社しない形でも、事前準備と手続きの流れを押さえておけば円滑に進められます。ここでは、即日退職を実現するために必要な準備と連絡の方法を解説します。
「明日からもう行かない」と退職を決めたらまずやるべきこと
まず最初に行うべきは、「退職の意思を明確に伝える準備」です。感情的に職場へ行かないと決める前に、退職届の作成や会社への連絡方法を整理しましょう。もし上司や人事と直接話すことが難しい場合は、書面やメールで退職の意思を伝える方法も有効です。重要なのは「退職の意思を伝えた事実」を証拠として残すことです。
会社への連絡手段(電話・メール・書面)の選び方
退職の意思を伝える手段として、最も確実なのは書面(退職届)または内容証明郵便です。口頭や電話でも退職意思は有効ですが、後から「聞いていない」と言われるリスクがあります。メールやLINEを利用する場合も、送信履歴を保存し、第三者が確認できる形で残しておくことが望ましいです。退職代行や弁護士を通じて通知を行う場合は、正式な書面として法的効力が認められます。ただし、突然内容証明郵便を送ると、会社側もびっくりしてしまいますので、まずは口頭で直属の上司に告げて、それでも話が進捗しない場合にこのステップに移るといいでしょう。
明日から行かない=即日退職を実現する3つの方法|退職代行を使うべきケース

会社に「明日から行かない」と即日の退職を実現するためには、状況に応じた正しい方法を選ぶことが大切です。退職には複数の手段があり、自力での交渉から退職代行までそれぞれ特徴とリスクが異なります。
特に精神的に追い詰められている場合や、会社が強引に引き止めてくる場合は、弁護士が対応する退職代行を利用することで、即日で安全に退職を成立させることが可能です。
方法1:自力での退職交渉(メリット・デメリット)
自力で退職交渉を行う方法は、最も費用がかからない反面、精神的な負担が大きいのが実情です。会社や上司との直接交渉では、「引き継ぎが終わるまで辞められない」「代わりが見つかるまで待ってほしい」といった引き止めを受けることも少なくありません。法的には退職の自由が認められているとはいえ、職場内での圧力や人間関係のストレスに耐える必要があり、結果的に退職が長引くケースもあります。
方法2:労働組合運営の退職代行(できること・できないこと)
労働組合が運営する退職代行では、労働組合法に基づく「団体交渉権」を利用して、会社とのやり取りを代行できます。ただし、交渉の範囲は「労働条件」などに限られ、個別の法的請求(未払い賃金・損害賠償など)は扱えません。また、組合への加盟が必要であり、即日退職に対応できないケースもあります。
労働組合型の業者は、もともとは民間の代行業者であったものが、法的に代行を行うために労働組合を結成したにすぎません。そのため、交渉にあたる担当者は弁護士でも法のエキスパートでもないことは留意してください。
方法3:弁護士運営の退職代行が最も確実な理由
弁護士による退職代行は、法的に認められた「代理権」を持つため、退職の意思伝達から交渉・請求まですべてを一括して行うことができます。会社が退職を拒否したり、損害賠償を請求してきた場合でも、弁護士が正式に対応できるため、依頼者がトラブルに巻き込まれる心配はありません。
また、未払い給与・残業代の請求も同時に進められるため、退職を機に権利を守りながら新しい生活をスタートできます。精神的な負担を減らし、最短で「明日から行かない」を実現できる方法です。
弁護士対応の退職代行なら会社に「明日行かない」が確実に叶う理由

「明日から会社に行かない」と決めたとき、最も安全かつ確実な手段が弁護士による退職代行です。弁護士は法律上の代理権を持ち、会社との交渉・通知・請求すべてを正式に代行できます。一般業者では対応できない法的トラブルにも即日で対応できるため、精神的にも経済的にもリスクのない退職を実現できます。
弁護士が担える「交渉」と「法的トラブル対応」の範囲
弁護士は、退職の意思伝達だけでなく、会社との交渉を法的に行うことができます。たとえば、「退職を認めない」「出社を強制する」といった違法な対応に対しても、法的根拠に基づいて退職の正当性を主張できます。さらに、内容証明郵便による退職通知や、退職日を正式に確定させる書面作成まで対応可能です。これにより、翌日からの出社義務が法的に消滅し、完全に職場から離れることができます。
未払い給与・残業代・退職金の請求代行
退職時に未払いの給与や残業代、退職金がある場合でも、弁護士が同時に請求を行うことができます。一般の退職代行ではこれらの請求は「非弁行為」となり、法的に扱うことができません。弁護士が対応すれば、退職手続きと並行して法的請求を進められるため、労働者の権利を確実に守ることができます。特にブラック企業においては、給与未払いがあるまま退職を引き止められるケースもあるため、法的手段を持つ弁護士への依頼が最も効果的です。
会社からの電話・訪問・実家への連絡を止められるのは弁護士だけ
退職を伝えた直後に、会社から電話やメールが繰り返し届く、上司が自宅に来る、あるいは実家に連絡が入るといったケースがあります。これらは精神的な負担を与えるだけでなく、プライバシーの侵害にもあたる行為です。民間の退職代行業者では、こうした不当な連絡を法的に止めることはできません。
一方、弁護士が介入している場合、会社に対して正式な「連絡禁止通知」を出すことが可能です。これにより、本人や家族への直接の電話・訪問・メールなどを法的に制限できます。もし企業側が通知を無視して連絡を続けた場合、弁護士を通じて警告書や損害賠償請求を行うことも可能です。弁護士の関与があるだけで、会社の対応が一変するケースは少なくありません。
即日から出社しないで退職する実際の流れ|相談から退職完了までのスケジュール

「明日から出社しない」という即日退職を成立させるためには、法的に有効な手続きの流れを理解しておくことが大切です。
弁護士または退職代行業者に依頼した場合、最短では当日中に会社への通知が完了し、1週間以内に退職が確定できるのが普通です。ここでは、即日退職の一般的な進行スケジュールを紹介します。
ステップ1:無料相談と契約(即日着手の重要性)
まずは退職代行サービスまたは弁護士事務所に相談を行います。多くの事務所では無料相談を実施しており、相談内容をもとに即日対応が可能かを判断します。依頼内容と費用が確定した後、正式な契約を締結することで即日着手が可能となります。
ステップ2:弁護士(または代行業者)から会社へ「退職通知」
契約が完了した後、弁護士や退職代行担当者が会社に対して正式な退職通知を送付します。通知手段は電話、FAX、または内容証明郵便などが一般的であり、通知が会社に到達した時点で退職の意思表示が法的に成立します。この時点から本人は会社と直接やり取りをする必要がなくなり、職場への出社義務も消滅します。
正式な退職日は会社との交渉や依頼者の希望に沿う形となりますが、退職日までの間は有給休暇の消化期間にあてられるのが一般的で、もし有給が既にない場合は、退職日が早まります(会社側も社会保険を払い続けなければならないため)。
ステップ3:退職に必要な書類のやり取りと完了
会社側が退職を受理した後、健康保険証や社員証などの返却物を郵送します。併せて、会社からは離職票や源泉徴収票などの必要書類が送付されます。弁護士が介入している場合は、これらの書類手続きもすべて法的に監督されるため、受け取り拒否や嫌がらせのリスクを防止できます。すべての手続きが完了すると、法的にも正式な退職が成立します。
退職時に必要な書類・返却物のリストと手続き上の注意点

退職を円滑に進めるためには、会社との書類や物品のやり取りを正確に行うことが重要です。とくに即日退職や退職代行を利用した場合、本人が直接出社できないケースも多いため、返却や受け取りの流れを明確にしておく必要があります。ここでは、退職時に必要となる代表的な書類や返却物、そして手続き上の注意点を整理します。
会社に返却が必要なものリスト(健康保険証・社員証など)
退職に際しては、会社から貸与されているすべての物品を返却する必要があります。代表的なものには、健康保険証、社員証、入館証、制服、業務用パソコンやスマートフォン、社用車、鍵などが含まれます。これらの返却は、退職日またはそれ以前に完了しておくのが原則であり、郵送による返却も可能です。紛失や破損がある場合は、速やかに弁護士または退職代行業者を通じて会社に報告し、トラブルを防ぐようにしましょう。
会社から受け取るべき書類と受け取り拒否された場合の対処法
退職後に会社から交付されるべき書類には、離職票、源泉徴収票、雇用保険被保険者証、年金手帳(預けていた場合)、退職証明書などがあります。これらの書類は今後の再就職や社会保険・失業給付の手続きに必須となるため、確実に受け取る必要があります。会社が発行や送付を拒否した場合は、弁護士を通じて正式な文書請求を行うことが可能です。書類の受け取りはすべて郵送で完結できるため、出社を求められても応じる必要はありません。
雇用形態別に見る会社に「明日から行かない」退職の可否と注意点

退職の自由はすべての労働者に認められていますが、雇用形態によって退職の可否や手続きの進め方に違いがあります。とくに即日退職を希望する場合、法律上の制約や契約内容によっては注意が必要です。ここでは、正社員・契約社員・派遣社員など、それぞれの雇用形態における会社に「明日から行かない」退職の可否と実務上の留意点を解説します。
正社員(期間の定めのない雇用)の場合
民法第627条に基づき、正社員は退職の意思を会社に伝えてから2週間が経過すれば、法的に退職が成立します。会社側が退職届を受理しない場合でも、通知が到達した時点で効力が発生するため、無断欠勤とみなされることはありません。弁護士を通じて内容証明郵便で退職届を送付すれば、翌日から出社義務を事実上なくすことも可能です。
契約社員・派遣社員(期間の定めのある雇用)の場合
契約社員や派遣社員の場合、契約期間中の一方的な退職は原則として認められていません。ただし、やむを得ない事由がある場合(パワハラ、健康悪化、給与未払いなど)は、民法第628条に基づき途中解約が可能です。こうしたケースでは、法的交渉権を持つ弁護士に依頼することで、安全に契約解除を進めることができます。民間の退職代行業者のみで進めた場合、契約違反とみなされるおそれがあるため注意が必要です。
業務委託・個人事業主契約の場合
業務委託契約は労働契約ではなく、民法上の「請負契約」または「委任契約」として扱われます。そのため、労働基準法による保護が及ばず、退職(契約解除)のルールも異なります。委任契約の場合は、民法651条によりいつでも解除が可能ですが、損害が発生した場合は賠償を求められる可能性もあります。弁護士を介して契約内容を精査し、解除通知の方法を正しく行うことが望ましいです。民間業者に依頼した場合「退職はできるけど違約金・賠償請求には対応してもらえない」という事態に陥るので、予め弁護士の退職代行に依頼するのがおすすめです。
弁護士法人みやびがサポートする即日退職|無料相談で確実に明日を変える

「明日から会社に行きたくない」「もう限界だけど、どう伝えればいいのかわからない」と悩む人は少なくありません。弁護士法人みやびでは、そのような状況にある方のために、即日退職のサポートを全国対応で行っています。法律の専門家である弁護士が直接対応するため、法的トラブルを防ぎながら安全かつ確実に退職を実現することができます。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら
退職後のトラブルも一貫サポート
退職が完了した後に会社から損害賠償請求を受けた場合や、離職票の発行を拒否された場合なども、弁護士が継続的にサポートします。退職の完了で終わりではなく、その後の生活を守るための法的ケアまで提供している点が、弁護士法人みやびの大きな強みです。
退職は新しい人生のスタートです。もし今「明日から行かない」と決意したなら、まずは弁護士法人みやびにご相談ください。無料相談から即日退職まで、経験豊富な弁護士が最短ルートでサポートします。
会社に明日から行かないで退職したい場合のよくある質問(FAQ)
「明日から会社に行かないで退職したい」「上司に何も言わず辞められるのか」と不安に思う方のために、即日退職に関するよくある質問をまとめました。法律的な観点から、弁護士監修の正しい情報をもとに回答しています。安全に退職を進めるための参考にしてください。
Q1. 「明日から会社に行かない」と言って本当に辞められますか?
はい。民法627条で「退職の自由」が認められているため、労働者は原則として自由に退職できます。特別な事情(パワハラ、賃金未払いなど)がある場合は、即日退職も可能です。会社の承諾は不要で、法的には退職通知を送付した時点で効力が発生します。
Q2. 弁護士に依頼すれば、翌日から出社せずに退職できますか?
はい。弁護士が介入すれば、当日中に会社へ正式な退職通知を送付できます。通知が会社に到達した時点で退職の意思が法的に成立するため、翌日以降の出社義務はなくなります。連絡や交渉もすべて弁護士が代行します。
Q3. 退職を伝えた後に会社から電話や訪問、実家への連絡があった場合は?
弁護士が介入している場合、会社に対して「連絡禁止通知」を出すことが可能です。これにより、本人や家族への電話・訪問・メールなどの連絡を法的に制限できます。無視して連絡が続く場合は、弁護士を通じて警告書や損害賠償請求を行うことも可能です。
Q4. 即日退職の場合、健康保険証や社員証などはどうやって返却しますか?
出社できない場合は、郵送での返却が一般的です。健康保険証・社員証・制服・業務用端末などをまとめて返送すれば問題ありません。弁護士や退職代行を通じて返却方法を伝えることで、トラブルを防ぎながら手続きを完了できます。
Q5. 離職票や源泉徴収票などの書類を会社が送ってくれない場合は?
これらの書類は会社の交付義務があります。弁護士が介入している場合、正式な文書で請求でき、受け取り拒否された場合でも郵送で取得することが可能です。出社を求められても応じる必要はありません。
Q6. 契約社員や派遣社員でも「明日から行かない」退職はできますか?
契約期間中の一方的な退職は原則として認められていませんが、パワハラ・健康被害・賃金未払いなどの正当な理由があれば途中解約が可能です。民法628条に基づき、弁護士が手続きを代行することで安全に契約解除を進めることができます。
Q7. 民間の退職代行と弁護士の退職代行は何が違いますか?
一般の退職代行業者は会社への「退職の意思伝達」までしか行えません。一方、弁護士による退職代行は、法的に認められた代理権を持ち、交渉・請求・トラブル対応まですべてを代行できます。損害賠償請求や書類の受け取り拒否などがあった場合でも、法的手段で対応できるのが大きな違いです。