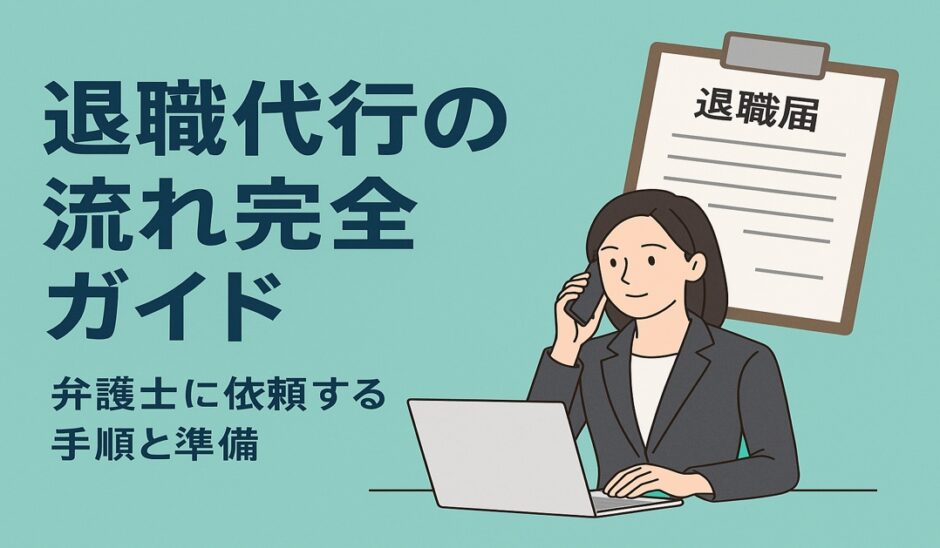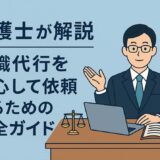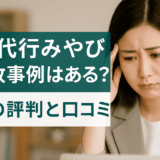退職代行を利用して退職したいけれど、「どんな流れで進むのか分からず不安」という方は少なくありません。退職代行サービスは、従業員本人に代わって会社へ退職の意思を伝え、必要な手続きを進める便利なサービスです。
弁護士に依頼する場合は、単なる意思伝達だけでなく、未払い給与や有給休暇の取得など法的な問題まで対応できる点が大きな特徴です。しかし、準備や書類、退職日までの手順を知らないまま進めると、思わぬトラブルや手続きの遅れにつながることもあります。ここでは、退職代行の全体の流れをステップごとに詳しく解説し、スムーズに退職するためのポイントや必要な準備まで徹底的にガイドします。これから退職を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
弊所「弁護士法人みやび」は全国にて退職代行サービスを実施している老舗の法律事務所です。退職代行の実績豊富なベテラン弁護士が対応させていただきますので、業界・業種・トラブル内容問わずお引き受けできます。まずはお気軽にご相談ください。
退職代行を弁護士に依頼したときの全体の流れ

退職代行を弁護士に依頼する場合の流れを理解しておくことは、トラブルを防ぎ、スムーズに手続きを進めるうえで重要です。弁護士による退職代行は、単に退職の意思を伝えるだけでなく、法的に対応できる点が大きな特徴です。従業員本人が直接連絡を取る必要がなく、未払い賃金や有給休暇の消化なども含めて対応してくれるため、安心して任せられます。ここでは、無料相談から契約、会社への連絡、退職当日、退職後の手続きまで、一連の流れを順を追って解説します。
STEP1:無料相談で状況や退職理由を伝える
まずは無料相談からスタートします。弁護士に連絡し、従業員本人の状況や退職理由、有給休暇の残日数、貸与されている備品の有無などを伝えます。この段階で、退職代行の流れや料金、対応できる範囲について説明を受け、不安や疑問点を解消します。特にパワハラや残業代未払いなど法的な問題がある場合は、この時に相談しておくことで、最適な対応が可能になります。相談は電話やメール、オンラインで行うのが一般的です。
STEP2:契約手続きと料金の支払いを完了する
相談内容に納得できれば、次は契約手続きです。弁護士と正式に契約書を交わし、料金を支払うことで正式に依頼が成立します。契約書には、退職代行業務の範囲や対応内容、料金、想定される退職日などが記載されます。料金の相場はおおむね5〜10万円程度で、支払い方法は銀行振込やクレジットカードが一般的です。契約内容をしっかり確認して署名し、支払いを完了させることで、いよいよ退職手続きが本格的に始まります。
STEP3:弁護士が会社に退職の意思を正式に伝える
契約が完了すると、弁護士が会社に対して退職の意思を正式に伝えます。内容証明郵便や電話など、法的に有効な方法で通知するため、従業員本人が直接連絡する必要はありません。この時点で、退職日や有給休暇の取得、備品の返却方法なども会社と調整されます。会社側が退職を拒否したり、連絡を無視したりするケースもありますが、弁護士が法的根拠をもとに対応するため、安心して任せられるのが大きなメリットです。
STEP4:退職日までに書類手続きと備品を返却する
会社との調整が終わり、退職日が決まったら、書類や備品の準備を進めます。退職届はもちろん、健康保険証や社員証、制服、パソコンなど会社から貸与されていた備品をまとめておきます。返却の際は郵送することが多く、追跡可能な方法で送り、控えを残しておくと安心です。業務の引き継ぎメモも簡単で構いませんので作成しておくと、会社側の不満を防ぎ、後のトラブルを避けられます。書類や備品の返却が滞ると手続きが遅れる場合もあるので、早めに準備しておくことが大切です。
STEP5:退職後に届く書類や有給休暇の処理
無事に退職が完了した後も、いくつかの重要な書類が自宅に届きます。離職票や源泉徴収票、退職証明書などは、失業保険や年末調整、次の就職先で必要になります。届くまでに時間がかかる場合もありますが、弁護士が会社に催促してくれるので安心です。また、退職日までに残っている有給休暇をすべて消化するのが基本です。残日数を事前に確認し、消化できるように弁護士に伝えておけば、給与に反映され、損をすることなく退職できます。社会保険や年金の切り替えなど、退職後の手続きも忘れずに行いましょう。
退職代行の流れをスムーズに進めるための準備と必要な書類

退職代行をスムーズに進めるためには、事前に必要な書類や備品の準備を整えておくことが重要です。退職代行を依頼したとしても、本人が用意しなければならないものはあります。準備が不十分だと、書類の未提出や備品の紛失といったトラブルにつながり、弁護士の対応が長引く原因にもなります。特に、退職届や貸与品のリスト、有給休暇の残日数は必ず確認しておきましょう。ここでは、具体的にどのような準備が必要か、ポイントを解説します。
退職届や貸与備品のチェックリスト
退職届は、退職の意思を示す正式な書類です。弁護士が内容証明で通知する場合もありますが、会社から提出を求められるケースもあるため準備しておくと安心です。併せて、健康保険証、社員証、PCやスマートフォン、制服、鍵などの貸与品はリストアップしておき、どこに保管しているかを確認します。特に高価な備品を紛失すると弁償を求められる場合もあるので注意が必要です。
業務引き継ぎメモや書類の整え方
退職後、会社から連絡が来るのを防ぐために、業務の引き継ぎメモを用意しておくと効果的です。担当していた業務の進捗状況や取引先の連絡先、重要なスケジュールなどを簡潔にまとめるだけでも、会社にとっては大きな助けになります。郵送する際は、メモや書類のコピーを残しておくと後で証明できるので安心です。
有給休暇の残日数も確認を
退職前に必ず有給休暇の残日数を確認しておきましょう。有給休暇は法律で認められた権利であり、退職日までにすべて消化するのが原則です。給与明細や勤怠記録で残日数を把握し、相談の際に弁護士に伝えておけば、会社との調整もスムーズです。残日数を把握していないと、消化しきれずに損をする場合もあるため、事前の確認が重要です。
退職代行の流れの中で起こりやすいトラブルとその解決策

退職代行の流れの中では、想定外のトラブルが発生することがあります。退職の意思を伝えた後に会社が拒否する、書類が送られてこない、備品の返却について不当な要求をされるなど、ケースはさまざまです。しかし、こうしたトラブルの多くは、弁護士が適切に対応することで解決できます。事前にどのような問題が起こりやすいかを知っておくことで、落ち着いて対処できるでしょう。ここでは、代表的なトラブルとその解決方法を解説します。
退職の拒否や連絡ミスへの対応
退職の意思を伝えたにもかかわらず、会社が「認めない」と拒否するケースがあります。しかし、労働者には退職の自由が法律で保障されており、会社が拒否する権利はありません。弁護士が内容証明郵便や電話で法的根拠をもとに伝えることで、問題は解決します。また、連絡ミスで意思が伝わっていない場合も、弁護士が確実に記録の残る方法で対応するので安心です。本人が直接対応する必要はありません。
書類未受領や備品トラブルのケース
退職後に離職票や源泉徴収票などが届かない、備品の返却について過剰な要求をされるといったトラブルもあります。これも弁護士が会社とやり取りし、書類の送付を求めたり、返却済みであることを証明したりして解決します。書類や備品の返却時には必ず控えや発送証明を残しておくと、後で役立ちます。会社からの一方的な請求や嫌がらせにも、法的に対抗可能です。
流れの終わりに必要な退職後の手続きと有給休暇の扱い

退職が成立しても、手続きが完全に終わったわけではありません。退職後には、各種書類の受け取りや社会保険・年金の切り替え、有給休暇の最終確認など、やるべきことが残っています。これらの手続きを怠ると、失業保険の申請や次の職場への提出書類が揃わず、後々困ることになります。退職後の流れも含めて理解し、必要な対応をしておきましょう。
離職票や源泉徴収票の受け取り方
退職後には、会社から離職票や源泉徴収票、退職証明書などが自宅に届きます。これらの書類は、失業保険の申請や年末調整、次の職場への提出に必要不可欠です。通常は数日〜2週間程度で届きますが、遅れることもあります。弁護士に依頼していれば、必要に応じて催促してもらえるため安心です。届いた書類は紛失しないように保管しましょう。
有給休暇や社会保険の手続きを忘れずに
有給休暇の残日数が正しく消化されているかも確認が必要です。弁護士が事前に調整していれば問題ありませんが、給与明細で確認すると確実です。また、退職後14日以内に健康保険や年金の切り替えを行う必要があります。健康保険証は会社に返却し、国民健康保険への加入か、家族の扶養に入る手続きを進めましょう。社会保険料や年金の納付漏れがないよう、早めに手続きを終えることが大切です。
退職代行の流れは民間業者と弁護士で違う?

退職代行サービスは、大きく「民間業者」と「弁護士」に分かれます。どちらも退職の意思を会社に伝えるという基本の流れは同じですが、対応できる範囲やサービスの内容に大きな違いがあります。ただし、トラブルが予想される場合や法的な交渉が必要なケースでは、弁護士でなければ対応できません。
民間業者の場合は、従業員本人に代わって退職の意思を会社に伝えるだけで、法的な交渉や金銭請求まではできません。そのため、未払い賃金や慰謝料請求が絡む場合には不向きです。弁護士に依頼した場合は、退職意思の伝達だけでなく、法的根拠をもとにした交渉が可能で、会社側が拒否したり、書類の送付を渋ったりしても適切に対処してくれます。つまり、弁護士の退職代行は、より強力で安全な選択肢と言えるでしょう。
退職代行は弁護士に依頼するのがおすすめ

結論として、退職代行を利用するなら弁護士に依頼するのが最も安心です。弁護士であれば、退職の意思伝達だけでなく、未払い給与の請求、有給休暇の消化交渉、さらにはパワハラや不当な損害賠償請求への対応も可能です。法的に認められた権限のもとで動いてくれるため、会社側も無理な要求や拒否をしにくくなり、スムーズに退職が進みます。
民間業者に比べると料金は高めですが、その分、確実性と安全性が段違いです。特に、トラブルのリスクが高い場合や、会社と直接連絡を取りたくない場合には弁護士が強い味方になります。準備をしっかり整え、信頼できる弁護士に相談することで、精神的な負担も軽くなり、円満に退職できるでしょう。自分の将来を守るためにも、弁護士への依頼を前向きに検討してみてください。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら
退職代行の流れに関するよくある質問
退職代行の流れや必要な準備、弁護士と民間業者の違いなど、よく寄せられる質問をまとめました。安心して退職手続きを進めるための参考にしてください。
質問:退職代行を弁護士に依頼すると、どのような流れになりますか?
無料相談から始まり、契約・料金支払い後に弁護士が会社に連絡します。その後、退職日や有給休暇の調整、書類・備品の返却、退職後の手続きまで進みます。
質問:退職代行を依頼したその日に会社に連絡してもらえますか?
弁護士や業者のスケジュール次第ですが、契約と料金の支払いが完了すれば当日中に連絡してもらえるケースが多いです。
質問:退職代行の依頼から実際に退職するまでにどのくらいの期間がかかりますか?
最短で即日退職も可能ですが、依頼者の希望退職日に沿って有給消化や備品返却の調整を行います。
質問:退職代行を利用する場合、こちらから会社に連絡する必要はありますか?
基本的には不要です。弁護士や業者がすべてのやり取りを代行し、必要に応じて会社と調整してくれます。
質問:退職代行の相談はどのタイミングで行えばいいですか?
退職を決めた時点で早めに相談するのが理想です。退職理由や有給の残日数、備品の有無などを整理しておくとスムーズです。
質問:弁護士に依頼すると料金はどのくらいかかりますか?
相場は5〜10万円程度です。契約書で業務範囲や料金を確認してから依頼しましょう。
質問:退職代行の準備として必要なものは何ですか?
退職届、貸与品リスト、業務引き継ぎメモ、有給休暇の残日数などを準備しておくと安心です。
質問:会社が退職を拒否した場合はどうなりますか?
労働者には退職の自由があり、会社が拒否する権利はありません。弁護士が法的根拠をもとに対応してくれます。
質問:退職後に必要な手続きは何がありますか?
離職票や源泉徴収票の受け取り、有給休暇の確認、健康保険や年金の切り替えなどがあります。弁護士が催促もしてくれます。
質問:民間業者と弁護士の退職代行の違いは何ですか?
民間業者は意思伝達までしかできませんが、弁護士は法的交渉や金銭請求も対応可能です。トラブルが予想される場合は弁護士がおすすめです。
質問:弁護士に依頼するメリットは何ですか?
未払い給与の請求、有給休暇の消化、パワハラ対応など法的に対応でき、会社が無理な要求をしにくくなるため、安心して退職できます。