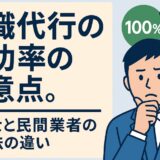「退職代行を依頼するなら弁護士か労働組合か」で迷う方は少なくありません。退職代行サービスには大きく分けて弁護士・労働組合・一般企業の3つの運営主体があり、それぞれ対応できる範囲や費用、メリット・デメリットが異なります。単に「辞められるかどうか」だけでなく、未払い賃金請求やハラスメント対応といった法的問題が絡むのか、それともスムーズに退職を進めたいだけなのかによって最適な選択は変わります。
本記事では弁護士と労働組合の退職代行を中心に、違いや判断基準をわかりやすく解説します。会社を辞めたいけどトラブルが心配、という人は、まずは弊所「弁護士法人みやび」へご相談ください。
退職代行サービスは弁護士・労働組合・民間業者の運営主体が実施。それぞれの特徴

退職代行と一口に言っても、実際には弁護士・労働組合・一般企業(民間業者)の3つの運営主体が存在します。それぞれが対応できる範囲や強み、料金体系は大きく異なるため、利用者が置かれている状況に合わせて適切に選ぶことが重要です。
弁護士による退職代行の特徴と対応範囲
弁護士による退職代行は、法的資格を持つため交渉や訴訟対応まで可能である点が最大の特徴です。未払い賃金や退職金請求など金銭トラブルに発展するケースでも安心して依頼できます。また、会社から損害賠償を請求された場合でも代理人として一貫して対応できるため、法的リスクを抱える退職希望者には最適な選択肢といえます。
労働組合・一般企業による退職代行の違い
労働組合が運営する退職代行は、団体交渉権を持ち会社と直接交渉できる点が強みです。非弁行為とならない正当性があり、料金も弁護士より安価に設定されることが多いです。一方、一般企業が運営する退職代行は、あくまで退職意思の伝達代行が中心で、交渉力や法的対応には限界があります。そのため、法的リスクがない場合や費用を抑えたいケースで利用されます。
弁護士による退職代行のメリット・デメリット

弁護士が行う退職代行は、他の運営主体にはない強みを持つ一方で、費用や期間に関するデメリットも存在します。ここでは弁護士を選ぶメリットとデメリットを整理し、どのようなケースで弁護士を利用すべきかを見ていきましょう。
退職代行の弁護士だからこそ可能な対応とメリット
弁護士は法律の専門家であり、退職代行において法的交渉が認められている存在です。未払い賃金や残業代の請求、退職金の支払い拒否への対応など、金銭請求を伴うトラブルを代理人として交渉できます。また、訴訟に発展した場合でも弁護士がそのまま対応できるため、依頼者が別途法律事務所を探す手間が不要です。また、ブラック体質の企業や高圧的な上司が相手でも、たいていの人間は弁護士から突然電話が掛かってきたら、委縮してこちらの要求はほぼすべて呑んでくれるものです。
退職代行の弁護士選択時のデメリットと注意点
一方で、弁護士への依頼は料金が高額になりがちというデメリットがあります。一般企業や労働組合の退職代行では3~5万円で済むケースが多いのに対し、弁護士の場合は5~8万円前後の費用が発生します。ただし、数万円程度の差でトラブルの心配なく安心して自宅で療養できるのだと考えたら、コスパは非常に高いと言えるでしょう。
労働組合による退職代行のメリット・デメリット

労働組合による退職代行は、団体交渉権に基づき会社と直接交渉できる点が大きな特徴です。弁護士よりも費用が抑えられるケースが多く、それでいて法的に交渉ができるため、グレーの民間業者と比較すると、労働組合型の方が昨今では人気があります。ただし、対応できる業務の範囲には限界があるため、事前に特徴を理解しておくことが重要です。
労働組合の団体交渉権とそのメリット
労働組合には団体交渉権が認められているため、会社に対して有給休暇の消化や退職時期の調整といった要求を交渉することが可能です。費用も弁護士に比べて安価に設定されている場合が多く、4万~5万円程度で依頼できるのが一般的です。また、労働組合は法律に基づいて活動しているため、非弁行為に該当することなく安心して依頼できる点もメリットといえます。
労働組合選択時の注意点とデメリット
労働組合型の退職代行にはいくつかの制限もあります。損害賠償請求や未払い賃金の回収など、法律上の交渉が必要な案件には対応できません。また、労働組合といっても、もとは民間の代行業者が法的にクリアになるために労働組合を結成したにすぎないため、実際会社と退職交渉する担当者は、法的知識や経験、実績が乏しいことが普通です。そのため、依頼者が期待するサポートが得られないこともあります。
弁護士に依頼すべきケース:法的トラブルが予想される状況

退職代行の依頼先として弁護士を選ぶべきかどうかは、トラブルの有無や企業体質によって判断されます。特に金銭的請求や契約上のトラブルが想定される場合や、責任者がワンマン社長であったり、高圧的な態度をとる人間の場合は、法律上の交渉や訴訟まで対応できる弁護士に依頼することが安全で確実です。
金銭的な請求が必要なケース
未払い残業代や賞与、退職金の支払いを拒否されている場合には、弁護士に依頼するのが適切です。これらの請求は法的根拠に基づいた交渉が必要となり、労働組合や一般業者では対応できません。また、有給休暇の消化を妨害されているケースでも、弁護士であれば法的な強制力を持って対応できます。
ハラスメント・契約上のトラブルがあるケース
職場でパワハラやセクハラを受けており損害賠償を求めたい場合や、理不尽な社長を相手にする場合も弁護士の出番です。さらに、会社側から逆に損害賠償を請求されそうな場合にも、弁護士が代理人となって対応することで、法的リスクを最小限に抑えることが可能です。
業務委託契約・有期雇用(契約社員など)のケース
競業避止義務や秘密保持契約に関するトラブルが予想される業務委託契約者も弁護士の退職代行がおすすめです。また、通常の民法が適用されない有期雇用社員の人も、民間業者や労働組合では荷が重いと言えるでしょう。
労働組合型に依頼すべきケース:危惧すべきトラブルが想定されない状況

退職に際して特別な法的トラブルが予想されない場合には、労働組合型の退職代行も現実的な選択肢の1つとなります。団体交渉権を持つ労働組合は、会社に対して正当な手続きを踏んで退職意思を伝えることができ、費用面でも弁護士より負担が少なく済む傾向があります。
一般的な退職代行で対応可能なケース
会社との間に深刻な法的トラブルがなく、退職の意思を伝えれば問題なく辞められるホワイト企業が相手であれば、労働組合型のサービスでも問題はないでしょう。アルバイトやパートタイムなども該当します。
弁護士や労働組合の退職代行業者選びで失敗しないためのチェックポイント

退職代行サービスは弁護士や労働組合型によって対応範囲や強みが異なるため、事前の情報収集と比較検討が欠かせません。費用の安さだけで判断すると、思わぬトラブルや追加負担が発生する可能性があります。安心して任せられるサービスを選ぶために、以下のポイントを確認しておきましょう。
退職代行を依頼する前に確認すべき基本事項
まず重要なのは運営主体が弁護士・労働組合・一般企業のいずれかを明確にすることです。どの主体に依頼するかで、交渉可能な範囲や法的対応の有無が変わります。また、料金体系が明確であるかどうかも必ず確認しましょう。追加費用の発生条件が曖昧なサービスは避けるのが賢明です。
退職代行完了後サポートで判断する
退職後に必要となる離職票や社会保険関連の手続きに対して、アフターフォローを提供しているかどうかも大切です。悪質な会社が相手の場合、退職完了後に会社から嫌がらせを受けることもありますので、代行完了後のサポート体制も業者の選定の基準となります。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら
退職代行を弁護士・労働組合に依頼する際のよくある質問
退職代行を利用する際、弁護士に依頼すべきか、それとも労働組合に頼るべきかで迷う方は少なくありません。ここでは、両者の違いやメリット・デメリット、よくある疑問点をQ&A形式でわかりやすく解説します。
Q:退職代行は弁護士に依頼したほうが安全ですか?
はい。弁護士は法律上の代理権を持っており、会社との交渉(未払い残業代請求、有給取得、損害賠償請求など)も法的に対応可能です。法的トラブルが想定される場合や確実に退職したい場合は、弁護士への依頼が安心です。
Q:労働組合による退職代行とは何が違いますか?
労働組合も団体交渉権を持つため、会社との交渉が可能です。ただし弁護士ほど法的な対応はできません。費用は安く抑えられる傾向があり、トラブルが少ない退職であれば労働組合の代行でも十分対応できます。
Q:弁護士の退職代行では未払い残業代も請求できますか?
はい。弁護士は法的な請求手続きを行えるため、未払い残業代や退職金などの金銭請求も可能です。金銭トラブルを抱えている場合は弁護士の代行が適しています。
Q:労働組合の退職代行でも有給休暇の交渉は可能ですか?
可能です。労働組合は団体交渉の枠組みで有給取得の申し出を行うことができ、多くのケースで会社側が対応に応じます。ただし、会社が拒否した場合に強制力を持つのは弁護士のみです。
Q:弁護士の退職代行はいくらぐらい費用がかかりますか?
相場は5万円〜8万円ほどです。加えて、残業代や退職金の請求などに対しては成功報酬(回収額の20%〜30%程度)がかかる場合があります。弁護士は何より対応範囲の広さとトラブル対応が魅力です。
Q:退職代行を使ったことが転職に不利になることはありますか?
基本的に不利になることはありません。退職理由や方法が転職先に知られることはなく、履歴書にも記載不要です。むしろ無断欠勤や揉めた末の退職のほうが悪印象になるリスクがあります。
Q:労働組合の退職代行は非正規雇用でも利用できますか?
はい。アルバイト・パート・契約社員など雇用形態に関わらず、労働組合の退職代行は利用可能です。雇用形態を問わず労働者としての権利が保障されています。
Q:退職代行で会社に訴えられる可能性はありますか?
通常はありません。正当な退職の権利に基づいている限り、法的に問題はありません。ただし退職時の損害が大きい場合や職場の機密情報漏洩などが絡む場合は注意が必要です。
Q:弁護士か労働組合か迷ったときの判断基準はありますか?
トラブルが想定される・金銭請求をしたいなら弁護士、辞める会社がホワイト企業、あるいはアルバイトやパートであれば労働組合が安くて適しています。不安があれば両者の無料相談を比較して決めるのがよいでしょう。