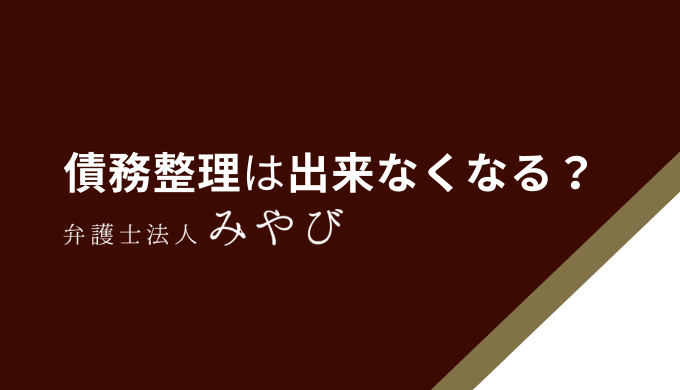※このページには一部広告を含みます。

「債務整理ができなくなるって聞いたけど、本当なのかな…」
「今まで何度も債務整理をしてきたけど、もう限界なのだろうか…」
このような不安を抱えている方は少なくないでしょう。
債務問題は早めの対応が重要です。
この記事では、借金問題に直面し将来の債務整理に不安を感じている方に向けて、
- 債務整理ができなくなる可能性がある状況
- 複数回の債務整理に関する制限と注意点
- 債務整理が難しい場合の代替手段
上記について、解説していきます。
債務整理は適切な条件下であれば何度でも可能ですが、状況によっては制限がかかることもあります。

この記事を参考に、あなたの状況に合った最適な解決策を見つける手助けになれば幸いです!
債務整理ができる
安いおすすめの事務所TOP3
弁護士法人東京ロータス法律事務所

※注意事項: 債務整理は個人の状況により最適な方法が異なります。まずは無料相談で専門家にご相談ください。
とお悩みの方へ
おすすめ事務所ランキング
本記事は、弁護士法人みやびの編集部が独自調査に基づき制作しています。監修弁護士は記事内の法的内容を確認していますが、掲載している弁護士事務所やサービスの選定には関与していません。また、この記事では編集部が独自に行なった債務整理が対応可能な弁護士・司法書士事務所28件を対象とした費用調査に基づき作成しています。(詳しく:任意整理費用の中央値分析〈2025年版〉)-弁護士法人みやび編集部)
本記事には一部プロモーションが含まれる場合がありますが、内容は編集部の独自方針に基づき作成しています。詳しくは 免責事項 および 制作ポリシー をご確認ください。
債務整理でクレジットやローンはどうなる?
債務整理をすると、一定期間はクレジットカードの新規作成やローン契約が難しくなります。
これは、債務整理の情報が信用情報機関に登録され、いわゆる「ブラックリスト」状態になるためです。
具体的には、完済後任意整理で約5年間、個人再生で約5〜7年間、自己破産で約7〜10年間、信用情報に記録が残ります。
以下で詳しく解説していきます。
ブラックリストとは何か?
「ブラックリスト」という言葉は、債務整理を検討する際によく耳にする言葉です。
実際には「ブラックリスト」という公式な名称のリストは存在しません。
これは一般的に「信用情報機関に事故情報が登録されている状態」を指す俗称です。
信用情報機関とは、個人の借入状況や返済履歴などの信用情報を管理している機関のことで、主に「CIC」「JICC」「全国銀行個人信用情報センター」の3つが日本では代表的です。
「ブラックリストに載る」とは、これらの信用情報機関に金融事故情報が登録されることを意味します。
金融事故情報とは、ローンやクレジットカードの支払い遅延、債務整理等の履歴などが該当します。
債務整理を行うと、その情報は信用情報機関に「事故情報」として必ず登録されるのです。
「債務整理をしたら一生ローンが組めなくなるのでは…」と心配される方もいるでしょう。
しかし、この情報登録は永久ではなく、債務整理の種類によって5〜10年程度で削除されます。
任意整理の場合は完済してから約5年、個人再生や自己破産の場合は約7〜10年が一般的な登録期間となっています。この期間が経過すれば、信用情報は回復し、新たなローン契約などが可能になる可能性が高まります。

ブラックリストは、あくまで一時的な信用情報の状態を示すものであり、将来的に債務整理ができなくなるわけではありません!
ブラックリストに載るとどう影響する?
ブラックリストに載ると、新たなクレジットカードの作成やローン契約が最長5〜10年間できなくなります。
これは債務整理の情報が信用情報機関に記録されるためです。
「ブラックリストに載ったら一生ローンが組めなくなる…」と不安に思う方もいるでしょう。
しかし、実際には永久に制限されるわけではありません。
ブラックリストに載ることで受ける主な影響は以下の通りです。
- クレジットカードの新規作成ができない
既存のカードも債務整理の手続き開始と同時に利用停止になることがほとんどです。 - 住宅ローンや自動車ローンなどの審査に通らない
信用情報に傷がついている状態では、大型ローンの審査は厳しくなります。 - 携帯電話の分割払い契約ができない
キャリア契約時の分割払いはローンの一種とみなされるため制限されます。 - 賃貸契約時の審査に影響する可能性がある
保証会社が信用情報を確認する場合、審査が厳しくなることがあります。
ただし、ブラックリストの情報は永久に残るわけではありません。
債務整理の種類によって異なりますが、情報は一定期間経過後に削除されます。
- 任意整理:約5年
- 個人再生:約5〜7年
- 自己破産:約7〜10年
この期間が経過すれば信用情報はリセットされ、再びローンやクレジットカードの利用が可能になります。
債務整理後も現金での支払いや、デビットカードの利用は可能です。
家族名義でのカード作成を検討する方もいますが、名義貸しにあたる可能性があるため注意が必要です。

ブラックリストに載ることは確かに生活に制約をもたらしますが、あくまで一時的なものと理解しておきましょう!
債務整理と住宅ローン・賃貸の関係性
債務整理と住宅ローン・賃貸の関係性は、多くの債務者にとって最大の関心事です。
債務整理を行うと、住宅や住まいの状況に大きく影響する可能性があるため、事前に正確な知識を持っておくことが重要です。
特に自己破産の場合は、所有している不動産が処分対象となるため、マイホームを失うリスクがあります。
一方、個人再生であれば住宅資金特別条項を利用することで、一定条件下でマイホームを維持しながら債務の整理が可能です。
賃貸物件に住んでいる方の場合も、債務整理の種類によって影響の度合いが異なります。
任意整理や個人再生では現在の賃貸契約に直接的な影響はありませんが、自己破産では保証会社との契約内容によっては更新時に問題が生じることもあります。
以下で詳しく解説していきます。
自己破産でマイホームはどうなる?
自己破産を行うと、原則としてマイホームを含む全ての財産は処分の対象となります。
債務整理の中でも最も強力な手段である自己破産では、債務者の財産を換価して債権者に配当するため、マイホームは失うことになるのです。
「自宅を守りながら債務整理したい」という方も多いでしょう。
しかし、自己破産の場合、住宅ローンが残っているマイホームは債権者のための担保財産となります。
住宅ローン特約により、破産手続きが開始されると金融機関は残債の一括返済を求めることができます。
これは「期限の利益の喪失」と呼ばれる条項によるものです。
マイホームを手放す具体的な流れは以下のようになります。
- 自己破産申立て後、裁判所が選任した破産管財人がマイホームの処分を行う
- 住宅ローンの残債を差し引いた価値がある場合は、その分が債権者への配当に回される
- 住宅ローンが完済済みの場合は、マイホームの全価値が債権者への配当となる
ただし、99万円以下の財産は「自由財産」として手元に残すことができます。
マイホームはこの金額を大きく超えるため、通常は保護されません。
「マイホームを絶対に守りたい」という場合は、個人再生などの他の債務整理方法を検討する必要があるでしょう。

自己破産でマイホームを失うことは、多くの方にとって大きな痛手です。
しかし、住宅ローンの返済に苦しむ状況から解放され、新たな生活を始めるための選択肢でもあります!
個人再生でマイホームを維持する方法
個人再生は、住宅ローンがある方でもマイホームを手放さずに債務整理できる手続きです。
個人再生手続きには「住宅資金特別条項」という制度があり、これを利用することでマイホームを維持したまま債務の整理が可能になります。
「住宅ローンがあるけど家は手放したくない…」と悩んでいる方にとって、個人再生は大きな救いとなるでしょう。
住宅資金特別条項を利用するための条件は以下の通りです。
- 住宅ローンの支払いが遅れていないこと
- 住宅ローンの残債務が住宅の価値を上回っていないこと
- 今後も住宅ローンの支払いを継続できる見込みがあること
この条件を満たせば、住宅ローン以外の債務(クレジットカードやキャッシング等)のみを減額対象とし、住宅ローンは従来通り返済を続けることができます。
個人再生で住宅を維持するメリットは、家族の生活基盤を守れることです。
特に子どもがいる家庭では、住み慣れた環境や学校区を変えずに済むため、家族への心理的負担を軽減できます。
また、住宅ローンの支払いが進んでいる場合、これまでの返済努力を無駄にせずに済むという点も大きなメリットです。
ただし、個人再生手続きには一定の費用がかかります。
弁護士や司法書士に依頼する場合の費用は約30〜50万円程度で、これに加えて裁判所への予納金も必要となります。
債務整理は将来的にできなくなるわけではありませんが、個人再生の場合は7年以内に再度利用することはできません。
住宅資金特別条項を利用する際は、専門家に相談して自分の状況に最適な方法を選ぶことが重要です。

マイホームを守りながら債務問題を解決するためには、早い段階での行動が何よりも大切なポイントとなります!
賃貸契約への影響はあるのか?
債務整理をした場合、現在の賃貸契約には基本的に直接の影響はありません。
賃貸借契約は債務整理の対象外となるため、手続きによって強制的に解約されることはないのです。
ただし、いくつか注意すべき点があります。
自己破産の場合、管財事件となると管財人が契約内容を確認することがあります。
また、家賃の支払いが滞っていると、債務整理とは別に賃貸借契約上の問題として退去を求められる可能性があるでしょう。
「債務整理をしたら今の家に住めなくなるのでは…」と心配される方もいるかもしれません。
しかし、債務整理自体が理由で強制退去させられることはないのです。
個人再生や任意整理の場合は特に問題なく、現在の賃貸契約を継続できます。
重要なのは、債務整理中も家賃の支払いを滞りなく続けることです。
家賃の支払いが困難な場合は、債務整理の計画に家賃も含めた生活設計を組み込むことが大切です。
弁護士や司法書士に相談して、無理のない返済計画を立てましょう。

現在の賃貸契約は、債務整理によって基本的に影響を受けないため、通常通り居住を継続できるでしょう!
新たな賃貸物件への入居は可能?
債務整理後も賃貸物件への入居は可能ですが、審査基準によって難易度が変わります。
信用情報機関に記録が残るため、大手不動産会社や厳格な審査を行う物件では入居審査に通りにくくなるでしょう。
「債務整理をしたら、もう新しい家に住めないのでは…」と不安に思う方もいるかもしれません。
しかし、完全に入居できなくなるわけではありません。
債務整理後の賃貸契約では、以下の対策が有効です。
- 保証人の確保
信頼できる親族や友人に保証人になってもらうことで、オーナーの不安を軽減できます。 - 保証会社の利用
審査基準が比較的緩やかな保証会社を選ぶことで入居のハードルを下げられます。 - 敷金・礼金の増額提案
家賃の数か月分を前払いするなど、オーナーにとってのリスク軽減策を提案します。 - 個人オーナーの物件を探す
大手不動産会社より柔軟な対応が期待できる個人オーナーの物件を優先的に探しましょう。
債務整理後の入居審査では、現在の安定した収入を証明できることが重要です。
最近の傾向として、保証会社によっては債務整理の情報よりも現在の収入状況を重視する場合もあります。

債務整理後も焦らず、条件に合った物件を探すことで、新たな生活の場を見つけることは十分可能です!
債務整理の仕事や家族への影響
債務整理を検討する際、多くの方が仕事や家族への影響を心配されます。
結論から言えば、債務整理の種類によって影響の度合いは異なりますが、適切に手続きを進めれば日常生活への大きな支障は最小限に抑えられるでしょう。
特に任意整理であれば、会社に知られることなく手続きを進められるため、仕事への影響はほとんどありません。
自己破産の場合でも、一般的な会社員であれば職を失うリスクは低いのです。
ただし、家族への影響については、共有財産の処分や連帯保証人になっている場合など、事前に確認すべき点があります。
例えば、配偶者が連帯保証人になっている債務の場合、あなたが債務整理をしても配偶者の返済義務は残ります。
また、自己破産では家族名義の財産が差し押さえられないよう、事前に所有関係を明確にしておく必要があるでしょう。
債務整理を検討する際は、家族との十分な話し合いと専門家への相談が重要です。
自己破産での職業制限について
自己破産を含む債務整理を検討する際、職業制限があるかどうかは重要な懸念事項です。
結論から言えば、自己破産をしても多くの職業は継続できますが、一部の資格や職業には制限が生じます。
自己破産すると、破産者として復権するまでの間(通常は免責決定から約10年間)、以下の職業に就くことができなくなります。
- 弁護士・司法書士・行政書士
法律関連の資格は破産者の就業が制限される代表的な例です。 - 税理士・公認会計士
財務や会計に関わる専門職も制限対象となります。 - 不動産鑑定士・宅地建物取引士
不動産取引に関わる資格も制限されます。 - 警備員
公安に関わる職種のため制限があります。
「自分の仕事はどうなるんだろう…」と不安に思う方も多いでしょう。
しかし、一般企業の会社員や自営業者、アルバイトなどは基本的に継続可能です。
公務員については、自治体や職種によって対応が異なるため、事前に確認が必要です。
また、破産手続き中は裁判所から許可を得なければ居住地を離れられないため、出張の多い職業の方は注意が必要です。
ただし、免責決定後はこの制限もなくなります。
重要なのは、自己破産による職業制限は一時的なものであり、復権後はすべての制限がなくなるという点です。

将来の職業選択に影響するかどうかを考慮して、債務整理の方法を選ぶことが大切です!
特定の債権者への返済は可能か?
債務整理中でも、特定の債権者だけに返済することは基本的に可能です。
ただし、債務整理の種類によって制限があります。
任意整理の場合は、交渉対象外とした債権者への返済を続けることができます。
例えば、住宅ローンは任意整理の対象から外し、通常通り返済を続けるケースが一般的です。
「住宅ローンだけは何としても守りたい…」と考える方も多いでしょう。
このような場合、任意整理は柔軟な対応が可能な手続きといえます。
個人再生においても、住宅ローンなど特定の債務を再生計画から除外して通常返済を続けることが可能です。
特に住宅資金特別条項を利用すれば、マイホームを維持しながら他の債務を圧縮できます。
一方、自己破産では平等な債権者間の公平性が重視されるため、特定の債権者だけに返済することは原則として認められません。
破産管財人が選任される場合は、すべての財産が管理下に置かれます。
ただし、自己破産でも親族への借金など、特別な事情がある場合は事前に返済しておくことが認められるケースもあります。この判断は非常に複雑なため、必ず弁護士に相談しましょう。

債務整理中の特定債権者への返済は、債務整理の種類や状況によって対応が異なるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です!
債務整理をしても変わらないこと
債務整理をしても変わらないことは多くあります。
債務整理は借金問題を解決する手段ですが、生活のすべての面に影響するわけではないのです。
多くの方が債務整理をすると人生のあらゆる面で制限を受けると心配しますが、実際には日常生活の多くの部分は変わりません。
戸籍や住民票に記載されることはなく、選挙権も維持されます。
例えば、自己破産をしても、あなたの戸籍に「破産者」という記載が残ることはありません。
また、健康保険や年金などの社会保障制度の利用資格も通常通り維持されるでしょう。
戸籍や選挙権への影響はあるか?
債務整理をしても、戸籍や選挙権に影響はありません。
これは多くの方が誤解している点です。
債務整理の手続きは、あくまで経済的な問題を解決するための制度であり、市民としての基本的権利には一切影響しません。
戸籍には債務整理に関する記載は一切されないため、結婚や就職の際の戸籍謄本取得でも、債務整理の事実が明らかになることはありません。
「債務整理をしたら戸籍に記載されて、将来に影響するのでは…」と心配される方もいらっしゃるでしょうが、そのような懸念は不要です。
選挙権についても同様に、債務整理の手続きによって制限されることはありません。
自己破産をした場合でも、選挙で投票する権利は完全に保持されます。
ただし、自己破産の場合は復権するまでの間、一部の資格や権利に制限が生じることがあります。例えば、以下のような制限があります。
- 後見人や保佐人になれない
- 会社の取締役などの役員になれない
- 弁護士や税理士などの特定の職業に就けない
これらの制限は通常、免責決定から10年程度で解除されますが、選挙権や戸籍に関する権利は最初から制限されません。

債務整理は経済的再生のための手続きであり、基本的人権や市民としての権利を奪うものではないことを覚えておきましょう!
仕事を失う可能性はあるのか?
債務整理をしても仕事を失うことはほとんどありません。
債務整理は借金問題を解決するための法的手続きであり、原則として雇用関係には直接影響しないためです。
一般企業に勤める会社員の場合、債務整理をしたことを会社に報告する義務はありません。
法律上、債務整理を理由とした解雇は不当解雇となる可能性が高いでしょう。
「債務整理をしたら会社にバレて解雇されるのでは…」と不安に思う方も多いかもしれませんが、実際にはそのようなケースはまれです。
ただし、一部の職業では影響が生じる場合があります。
- 金融機関勤務者
信用情報機関への登録により、業務に支障をきたす可能性があります。 - 宅建業者・保険外交員
自己破産の場合、一定期間資格制限を受けることがあります。 - 公務員
懲戒処分の対象となる可能性がありますが、ケースバイケースです。
会社への影響を最小限にするなら、任意整理や特定調停といった穏便な方法を選ぶことも検討できます。
これらの方法なら、官報に掲載されないため、会社に知られる可能性は低くなります。

債務整理を検討する際は、雇用への影響も含めて弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
適切な債務整理方法を選ぶことで、仕事を続けながら借金問題を解決できるケースがほとんどです!
税金や保険の扱いについて
債務整理を行っても、税金や社会保険料の支払い義務は基本的に残ります。
これらは特別な扱いを受ける債務だからです。
自己破産の場合でも、税金や社会保険料は非免責債権として残ることが一般的です。
特に国税や地方税の滞納分は、免責許可決定後も支払い義務が継続します。
「税金も全て免除されるのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、実際はそうではありません。
ただし、個人再生や任意整理では、通常の債務と同様に返済計画に組み込むことが可能な場合もあります。
国民健康保険や国民年金の滞納分についても、債務整理後も支払い義務は残ります。
これらは生活の基盤となる重要な制度であるため、特別な扱いを受けるのです。
税金や保険料の滞納がある場合は、債務整理と並行して分割払いなどの相談をすることをお勧めします。
- 自己破産でも免除されない税金の例
所得税、住民税、固定資産税など国税・地方税の多くが該当します。 - 社会保険関連で残る債務
国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料などが該当します。

債務整理後も税金や保険料の支払い義務は残るため、計画的な返済が必要となります!
海外旅行は可能か?
債務整理後も海外旅行は基本的に可能です。
債務整理は旅券(パスポート)の発行や更新に直接影響しないため、海外旅行の権利自体は制限されません。
ただし、自己破産の場合は手続き中に裁判所から海外渡航の制限を受けることがあります。
これは破産管財人による財産調査が完了するまでの一時的な措置です。
「自己破産したら二度と海外に行けなくなるのでは…」と心配される方もいるでしょう。
しかし、免責許可決定後は渡航制限がなくなるため、通常通り海外旅行を楽しむことができます。
個人再生や任意整理の場合は、手続き中であっても海外旅行に関する特別な制限はありません。
ただし、実務上の注意点として以下が挙げられます。
- 返済計画中の場合:毎月の返済を確実に行うことが前提です
- 海外旅行費用の捻出:返済中の無理な旅行は避けるべきでしょう
- 裁判所への報告義務:自己破産中の長期渡航は裁判所に報告が必要な場合があります

債務整理後の海外旅行は法的には問題ありませんが、返済計画を優先し、計画的な旅行を心がけることが大切です!
債務整理に関するよくある質問
多くの方が、債務整理に関して不安や疑問を抱えています。
特に「今後債務整理ができなくなるのではないか」という心配をされる方も少なくありません。
このような不安は、債務整理の仕組みや影響について正確な情報を得ていないことから生じることが多いでしょう。
債務整理は法律で保障された権利であり、今後も継続して利用できる制度です。
任意整理後の生活への不安や、ブラックリスト期間の長さ、債務整理後の生活を支える工夫など、具体的な疑問点について多くの相談が寄せられます。
以下で詳しく解説していきます。
任意整理後の生活に不安はある?
任意整理後の生活は基本的に通常どおり続けられますが、いくつかの制約があります。
クレジットカードやローンなどの借入れが一定期間困難になるため、キャッシュレス決済の利用に制限が生じるでしょう。
「任意整理をしたら生活が一変してしまうのでは…」と不安に思う方もいるかもしれません。
しかし、実際には日常生活のほとんどは変わりません。
任意整理後の主な制約は以下の通りです。
- 信用情報機関に金融事故情報が登録される
これにより完済から約5〜7年間は新規借入れが難しくなります。 - クレジットカードが使えなくなる
既存カードは解約となり、新規作成も一定期間できません。 - デビットカードや電子マネーへの移行が必要
現金主体の生活に戻るか、これらの代替手段を活用することになります。
一方で、任意整理後も変わらないことも多くあります。
- 給与や資産は基本的に維持できる
- 住居や家財道具などの生活基盤は守られる
- 仕事や職業選択に制限はない
- 家族や周囲に通知されることはない
任意整理後の生活を乗り切るためには、現金管理の徹底や家計簿をつけるなど、計画的な家計運営が重要です。
債務の重荷から解放されることで、精神的な安定を取り戻せる点は大きなメリットといえるでしょう。
任意整理後の生活は一時的な制約はあるものの、借金問題解決による安心感と共に、健全な金銭感覚を身につける機会にもなります。
ブラックリストの期間はどれくらい?
ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)の登録期間は、債務整理の種類によって異なります。
一般的に、任意整理は5〜7年、個人再生は5〜10年、自己破産は7〜10年程度続きます。
この期間中は新たなローンやクレジットカードの審査に通りにくくなるため、「もう二度とローンが組めなくなるのでは…」という不安を抱える方も多いでしょう。
しかし、ブラックリストは永久に続くものではありません。
登録期間が終了すれば、信用情報は自動的にクリアされます。
期間中も、以下の方法で信用回復を早めることができます。
- 公共料金や家賃の支払いを滞りなく続ける
- デビットカードや少額のクレジットカードを利用して返済実績を作る
- 安定した収入を維持する
特に任意整理の場合は、和解した債権者への返済を計画通り続けることが重要です。
これにより、「この人は返済能力がある」という信頼を少しずつ取り戻せます。
ブラックリスト期間中も、現金での生活は十分可能です。
期間終了後は新たなスタートを切れるため、この時間を財務管理の見直しや貯蓄習慣の確立に充てることをお勧めします。
ブラックリストは一時的なものであり、必ず終わりがあることを覚えておきましょう。
債務整理後の生活を支える工夫
債務整理後の生活を立て直すには、計画的な家計管理と新たな収入源の確保が重要です。
まず、収支バランスを見直し、無駄な支出を削減することから始めましょう。
固定費(家賃・光熱費・通信費など)の見直しは大きな節約につながります。
「もう二度と借金生活には戻りたくない…」という思いを胸に、生活スタイルの見直しを進めていきましょう。
具体的な生活改善策としては以下のポイントが効果的です。
- 家計簿アプリの活用:
日々の支出を記録し、無駄な出費を可視化することで節約意識が高まります。 - 副業の検討:
本業以外の収入源を確保することで、家計の安定につながります。 - 貯蓄習慣の確立:
給料日に先取り貯蓄を行い、緊急時の備えを少しずつ構築していきましょう。 - 節約コミュニティへの参加:
同じ境遇の人との情報交換は、新たな節約術の発見につながります。
債務整理後は、クレジットカードやローンが使えない期間がありますが、これを「キャッシュレス依存からの脱却期間」と前向きに捉えることも大切です。
現金払いを基本とした生活は、支出を実感しやすく、計画的な家計管理の基礎となります。
また、専門家のサポートを活用することも有効な手段です。
- ファイナンシャルプランナーへの相談:
中長期的な資産形成や家計改善のアドバイスが得られます。 - 法テラスなどの無料相談窓口:
債務整理後の生活再建に関する法的アドバイスを受けられます。
債務整理は終わりではなく、健全な経済生活を送るための新たなスタートです。
まとめ:債務整理の制度変更と今後の動向
今回は、将来の債務整理制度に不安を感じている方に向けて、
- 債務整理制度の現状と今後の見通し
- 債務整理が制限される可能性とその背景
- 債務問題を抱えている方が今すべき対応策
上記について、解説してきました。
債務整理制度は完全になくなる可能性は低いものの、今後は利用条件が厳格化される可能性があります。
経済状況や社会情勢の変化に伴い、法制度も適宜見直されていくのは自然なことでしょう。
債務問題を抱えている状況は非常に苦しく、将来への不安も大きいことでしょう。
これまで返済のために努力してきたことは、決して無駄ではありません。
今後も債務整理制度は形を変えながらも、経済的に困窮している方を救済する重要な制度として存続していくはずです。

まずは専門家への相談を第一歩として、自分に合った解決策を見つけていきましょう!